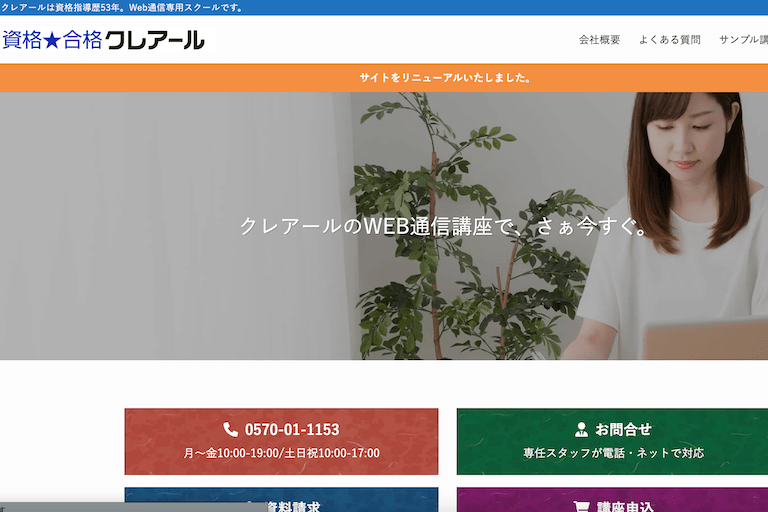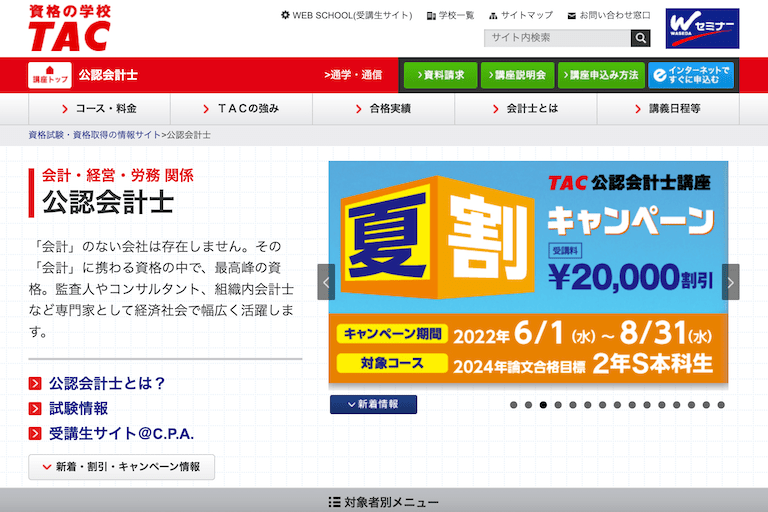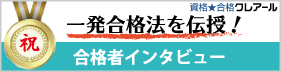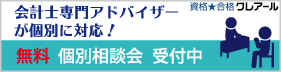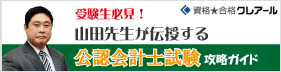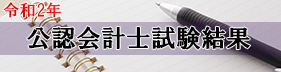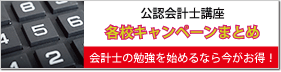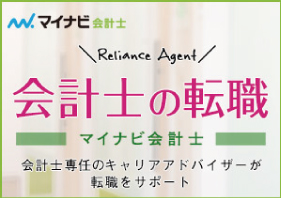日本公認会計士協会は日本で唯一の公認会計士の団体で、公認会計士は会員になることが必須とされています。
では、日本公認会計士協会とはどんな組織で、どんな活動を行っているのでしょうか。
今回は日本公認会計士協会について詳しく紹介していきます。
日本公認会計士協会とはどんな機関?

日本公認会計士協会は、日本で唯一の公認会計士の団体です。
日本公認会計士協会の発足は1949年と古く、公認会計士の自主規制機関としての役割を担っています。
協会の会員は、公認会計士(外国公認会計士を含む)と監査法人で構成されており、日本のすべての会計士・監査法人は日本公認会計士協会に加入しています。
現在は全国に16の支部(地域回)を持ち、各地域会に密着した活動を行っています。
公認会計士協会員のデータ
年齢別会員数割合
2021年12月31日現在の公認会計士協会員の年齢別割合は下表のとおりです。
最も多いのは40代で全体の会員数の約3分の1を占めています。
次に、30代、50代、60代以上と続いており、20代以下の会員数の割合が最も小さくなっています。
公認会計士協会の正会員となるには、論文式試験合格後に実務補習や実務経験などを通常3年間積む必要があり、試験突破が速い人でも25歳前後にようやく正会員となることができるため、20代以下での会員数が少なくなっているのです。
| 年齢層 | 会員数 | 割合 |
|---|---|---|
| ~20代 | 1,487人 | 4.4% |
| 30代 | 9,904人 | 29.8% |
| 40代 | 10,636人 | 32.0% |
| 50代 | 5,730人 | 17.3% |
| 60代~ | 5,454人 | 16.5% |
会員数推移
会員数は公認会計士協会の発足以降、増加し続けており、直近年度の2021年度では4万人を超えて40,201人(準会員+正会員)となっています。
2008年頃から2010年頃にかけて、政策的に公認会計士試験の合格者数を増加させたこともあり、2000年度から2010年度、2020年度にかけて会員数は他の年度と比較しても大きく増加しました。
| 年度 (12月末時点) |
準会員数 | 正会員数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 44人 | 241人 | 285人 |
| 1960年 | 733人 | 1,244人 | 1,977人 |
| 1970年 | 525人 | 4,220人 | 4,745人 |
| 1980年 | 2,107人 | 6,127人 | 8,324人 |
| 1990年 | 2,393人 | 8,927人 | 11,320人 |
| 2000年 | 4,038人 | 13,375人 | 17,413人 |
| 2010年 | 8,596人 | 21,496人 | 30,092人 |
| 2020年 | 6,454人 | 32,744人 | 39,198人 |
| 2021年 | 6,719人 | 33,482人 | 40,201人 |
日本公認会計士協会の沿革
日本公認会計士協会は、1949年(昭和21年)に任意団体として発足しました。
そして、1966年に公認会計士法で特殊法人として定められ、2004年には特別な法に基づいて民間法人化された特別民間法人という現在の組織形態となります。
特別民間法人は、その事業の公共性から特別の法律により設立された民間法人で、特徴として、国が出資や役員任命を行わないことが挙げられます。
特別民間法人としては、他には日本商工会議所や農林中央金庫などがあります。
社会的役割と仕事内容
日本公認会計士協会の役割は、監査証明業務の改善進歩を目的とした会員の指導や監督です。
そのために、公認会計士業務に関する講習会・研究会の開催や、監査や会計に関する研究調査などの事業を行っています。
公認会計士協会は公認会計士が組織する「自主規制機関」という位置づけで運営されており、会員の規律を正し、会計士としての能力を一層向上させるために指導を行っています。
倫理規則
その自主規制機関として最も重要な役割を果たすのが、日本公認会計士協会が定める倫理規則です。
会員であるすべての公認会計士はこの倫理規則に従って業務を行う義務があります。
このような職業倫理に係る規則の整備を通して公認会計士のあるべき姿を示し、公認会計士の信頼性や社会的地位の向上に貢献しています。
倫理規則の制定のほかにも、公認会計士や監査法人の実際の業務結果を事後的にレビューする業務も実施しており、公認会計士が実施する業務の品質を担保する役割も担っています。
研究調査
また、重要なもう一つの役割として、監査や会計に関する研究調査があります。
公認会計士は、定められた会計・監査の基準に従って業務を実施します。
しかし、会計・監査の基準は一般的な原則・事項が定められているのみで、個々の企業の状況によっては、どのように基準を適用すべきか不明確な状況になることが少なくありません。
そこで、公認会計士協会は、会計や監査の基準を読み解く役割を果たしており、具体的には実務指針や研究報告を公表することで、公認会計士が実際の業務で会計や監査の基準を適用するうえで、従うべき指針となるものを作成・公表しています。
一般企業向けの情報開示・支援
さらに、このような公認会計士に向けた事業だけでなく、一般企業に向けた情報開示や支援も協会の仕事です。
公式HPでは、社外役員として公認会計士登用を検討している企業に対し公認会計士を紹介する制度を設けたり、中小企業の事業を支援するためのツールを紹介したりと、幅広く事業を行っていることがわかります。
会計・監査に関する専門知識を有する公認会計士団体として、日本経済に関わる幅広く重要な業務を行っていると言えるでしょう。
公認会計士協会の会員になるメリットとは
公認会計士法において、公認会計士及び監査法人は当然に日本公認会計士協会の会員になると定められており、メリットの有無に関わらず、公認会計士として働くのであれば会員にならないという選択はできません。
加入義務があるとはいえ、公認会計士協会の会員となるメリットは多くあります。
まず、日本公認会計士協会の地域会において、研修やセミナーが不定期で開催されており、職業的専門家としての知識・能力の向上に役立てることができます。
また、毎年、研究大会と言われる、公認会計士や外部有識者、実務家等の研究成果等を全国から参集し発表するイベントも開催しています。
その他、地域ごとに公認会計士同士の交流イベントを頻繁に開催しているため、人脈を広げることができるのも大きなメリットの一つでしょう。
また、各地域支部の公式サイトでは、会計士試験の合格者が通う「実務補修」に関するお知らせや、様々な研究調査の結果報告を見ることが可能であり、自身の公認会計士としての活動に有益な情報を集められるメリットがあります。
公認会計士協会の会員にならない場合の罰則は?
既に述べたとおり、公認会計士は当然に日本公認会計士協会の会員になると法律で定められています。
実際に公認会計士試験の合格後に資格登録の手続きを行うのは日本公認会計士協会です。
日本公認会計士協会が管理する公認会計士名簿に登録されて初めて公認会計士となり公認会計士としての業務を行うことができるようになります。
そのため、まず公認会計士協会にならないという選択をすることは不可能でしょう。
そのため、公認会計士協会の会員にならないことに対する罰則の定めはありません。
ただし、公認会計士としての登録がないままに、公認会計士業務を実施した場合には、場合によって、詐欺等の刑事上の責任のほか、民事上の損害賠償請求や業務停止等の行政処分の対象となることが考えられます。
会長は四大監査法人の代表であることが慣例
日本公認会計士協会の会長職は任期3年で初代は太田哲三氏(現EY新日本有限責任監査法人)です。
2022年度からはEY新日本有限責任監査法人の茂木哲也氏が就任しており、4代監査法人の代表社員から選任されるのが慣例となっています。
登録費用は無料?
日本公認会計士協会に登録するには費用が必要となります。
これは、公認会計士協会を運営していくための費用に充てられ、会員のみならず準会員も発生します。
ただし、監査法人や事業会社で働く公認会計士の場合は法人側で会費を負担していることが多いです。
これまで公認会計士協会の会費は年間60,000円でしたが、40年ぶりに値上げを行い2020年4月から年間70,000円となっています。
| 月額 | 年額 | |
|---|---|---|
| 会員 | 6,000円 | 72,000円 |
| 準会員 | 1,500円 | 18,000円 |
公認会計士・監査審査会(CPAAOB)とは異なる専門機関

公認会計士の団体として、「公認会計士・監査審査会(CPAAOB)」という団体があります。
公認会計士・監査審査会は、公認会計士法に基づき金融庁に設置された公的機関であり、民間団体である日本公認会計士協会とは全くの別物となります。
なお、公認会計士・監査審査会は会長1名と委員9名で構成されています。
CPAAOBの概要と役割
公認会計士・監査審査会(CPAAOB)の役割は、大きく分けて3つあります。
公認会計士の業務の品質の監督、公認会計士試験の実施、公認会計士に対する懲戒処分などの調査・審議です。
公認会計士を目指す人が一番関わるのは「公認会計士試験の実施」でしょう。
試験の出願から試験結果の発表まで全て公認会計士・監査審査会が行っています。
反対に、公認会計士になった後の研修などは日本公認会計士協会が行っているため、会計士試験を突破した人が多く関わるのは公認会計士協会の方だと言えるでしょう。
会計士として働き始める際には必ず登録
公認会計士試験を突破した人は、協会に「準会員」として登録されます。
その後、所定の実務経験(業務補助)と実務補習所の補習を受け、協会が行う修了試験に合格したものが正式な会員として登録されることになります。
この登録をもって初めて、正式に公認会計士として名乗れるのです。
公認会計士協会は、この登録に関する諸手続きを行っており、また、支部によっては労働者の介護休業制度の紹介など、働く上で重要な公的制度の案内を公式サイト上で行っています。
会計士という職種に限らず社会で働く上で必要な情報も提示してくれているため、自分が所属する公認会計士協会の支部会ホームページを時折チェックしてみるのも良いでしょう。
協会のCPE「継続的専門研修制度」とは

公認会計士は高度な知識とスキルを有する専門職として、常に最新の法令・基準や会計知識を取得して会計士としての品質や信頼を維持しておく必要があります。
そこで、公認会計士協会では、平成14年からCPE(Continuing Professional Education)と呼ばれる継続的専門研修制度を設けています。
継続的専門研修制度CPEでは、直近3事業年度で合計120以上の単位を取得することが義務となっており、単位取得の方法は、公認会計士協会主催の研修会、自己学習、著書執筆、セミナー講師などで単位を取得することが可能です。
自己学習とは、公認会計士協会が発行する「会計・監査ジャーナル」にCPE指定記事があるので、そちらを読んで感想や概要説明などを書くことで単位が取得できます。
監査法人に勤務する公認会計士は、監査法人内部の研修やe-learningなど学習環境が用意されているため、比較的容易ですが、それ以外の場合は個人で時間を見つけて研修を受ける必要があるため、仕事と両立しながらの受講は決して容易ではありません。
ただし、CPEの単位取得を怠った場合は指示または公表されるペナルティも用意されているので注意しましょう。
事業会社に勤務または独立開業などの公認会計士は、公認会計士協会からは定期的に研修の案内が届くので、積極的に参加したり、自己学習を時間を見つけて実施することをおすすめします。
また、公認会計士協会意外にもCPEが認定する民間研修もあるので、興味があるのは参加して効率よく単位を取得していくことが大切です。
公認会計士協会で働けるの?
日本公認会計士協会では、協会事務局で働く人材を募集しており、中途・新卒採用も実施しています。
注目すべき事項が、公認会計士の資格は必要でないことです。
しかし、会計や監査の知識が要求される場面も多く、試験勉強の知識や経験を活かすことは大いに可能です。
ここでは、日本公認会計士協会の採用について詳しく確認していきましょう。
主な業務内容・勤務地域
日本公認会計士協会の事務局で働く場合、主な業務として委員会業務があります。
これは公認会計士や専門家の委員をサポートする業務で、指針の策定などの管理・運営があげられます。
また、他にも協会運営に必要不可欠な官公庁との折衝・出版・広報・総務といったように仕事は多岐に渡るのが特徴です。
上記の他にも、公認会計士制度の施策や、会計・監査の調査研究など協会特有の仕事もあり、公認会計士試験に合格できなかったものの、関係する業界で働きたいという人にもおすすめかもしれません。
採用・求人データ
ここでは2022年向けの日本公認会計士協会が募集する新卒採用の情報を紹介します。
過去の採用データも一緒に紹介しますので、日本公認会計士協会に興味がある方はぜひ確認してみて下さい。
なお、採用については、リクナビ等の新卒向けまたは転職エージェントからエントリー可能です。
| 採用人数 | 1~5名 |
|---|---|
| 職種 | 総合職(四大卒) |
| 勤務地 | 東京都千代田区九段南4-4-1 公認会計士会館 |
| 給与 | 四大卒:月給241,638円 院卒:月給261,818円 ※2020年実績 |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回 |
| 平均勤続年数 | 10.2年(2020年時点) |
| 平均年齢 | 42.2歳(2020年時点) |
まとめ
今回は、日本公認会計士協会について紹介してきました。
唯一の自主規制団体であり、監査や税務・コンサルティングなどの「あるべき姿」を提示し、ルール作りや会計士として品質向上に努めています。
監査法人での活躍を見て公認会計士を目指している方が多いですが、協会の事務局でサポートするという働き方もあります。
この機会に日本公認会計士協会について詳しく確認してみると良いでしょう。