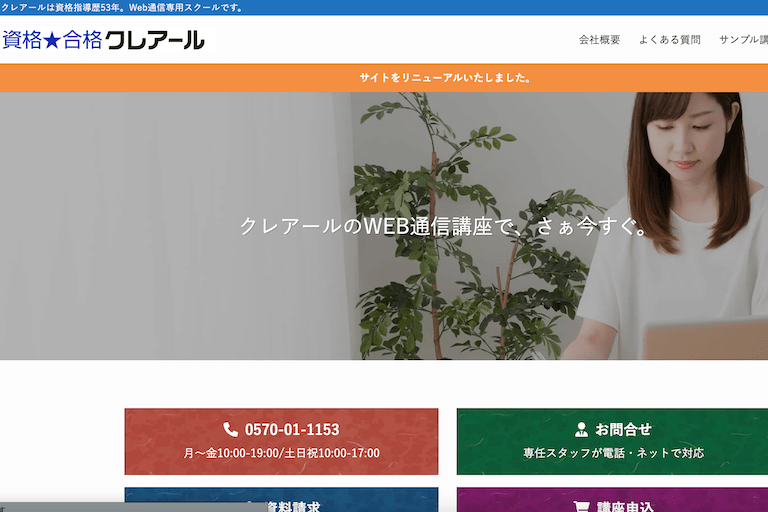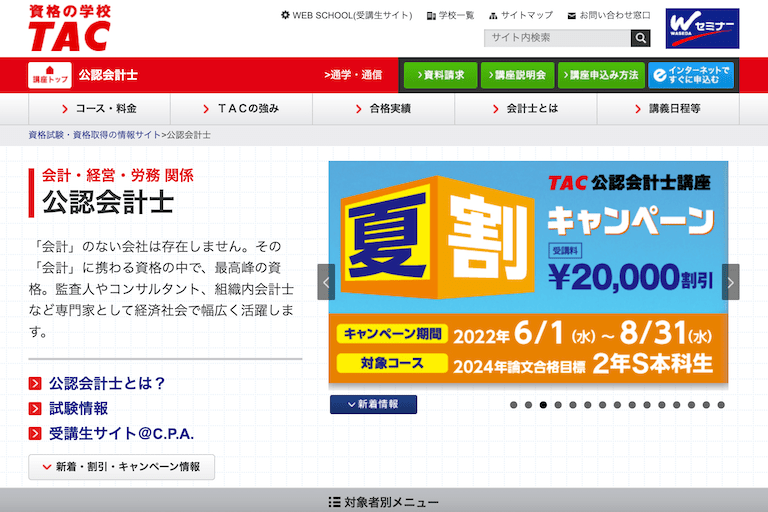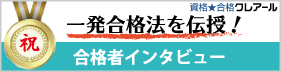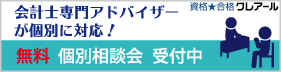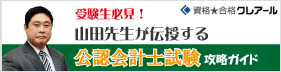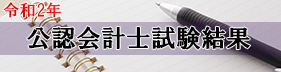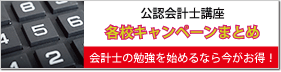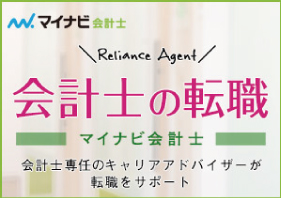会計資格の最高峰と呼ばれる公認会計士は、高度な知識と専門スキルを有しているため、合格後は監査法人以外の多方面で活躍可能です。
今回は、そんな安定した地位と報酬を得やすい公認会計士とはどんな資格や仕事があるのかを簡単にわかりやすく解説していきます。
公認会計士とは
公認会計士とは監査および会計に携わる専門家で、弁護士や医師と並ぶ最難関の国家資格として知られています。
公認会計士としての仕事は、企業の会計を第三者の立場から監査することが主になります。監査とは、企業が外部に発表する財務諸表(財務・会計に関する情報)が正しいのかチェックをすることです。
こういった企業の財務・会計に関する情報は資本市場に大きな影響を与えるものであり、会計のプロフェッショナルの立場から情報の信頼性を判断するのが公認会計士の大きな役割となります。
公認会計士とは、数ある会計系資格の中でも最高峰と言われており、試験合格率は毎年10%前後と非常に低いです。
しかし、難関試験を突破すれば公認会計士として専門職につける、いわゆる「手に職をつける」ことができるため、公認会計士を目指す方は少なくありません。
近年では女性の合格者が約20%と目立ってきており、多くの女性が現場の最前線で活躍する機会も増えています。
公認会計士になるには?正会員になるまでのキャリアパス

公認会計士試験は短答式試験と論文式試験の2段階形式で実施されます。
しかしながら、論文式試験に合格するだけでは公認会計士になることはできません。・
公認会計士になるには、「正会員」として正式に認められる必要があり、大きく次の4つのステップをすべてクリアしなければなりません。
- 公認会計士試験の合格
- 実務経験2年
- 実務補習所への通学
- 修了考査への合格
公認会計士試験合格
先述のとおり、公認会計士試験は短答式と論文式の2段階形式の試験になっています。
短答式試験は年2回(12月と5月)、論文式試験は年1回(8月)実施されており、公認会計士志望者はまず短答式試験を合格し、次に論文式試験を突破する必要があります。
実務経験2年
公認会計士試験合格後は、監査法人や企業で2年間(※)の実務経験を積む必要があります。
実務経験を積むためには、大きく2つの方法があります。
「業務補助」もしくは「実務従事」です。
業務補助とは、公認会計士又は監査法人の監査証明業務に携わり、その補助の役割を果たすことです。
多くの試験合格者は、監査法人に就職し実際に監査証明業務に携わることで、この要件を満たしています。
実務従事は、事業会社等に常勤として勤務し、なおかつ、その業務内容が法令で定められた業務として認められた場合に、この要件を満たすことができます。
※令和4年(2022年)5月に公認会計士法が改正され、実務経験の必要年数が2年から3年に変更されることとなっています。具体的な適用時期や適用方法は現状不明のため、これから目指す人は今後の動向にご注意ください。
実務補習所への通学
論文式試験合格後は2年の実務経験を積むとともに、実務補習所で原則3年間の実務補習をうけ、所定の単位を取得する必要があります。
実務補習所は実務経験を積みながら通う塾・予備校のような場所で、講義形式はライブ講義のほかe-learnning、ディスカッションなどがあります。
このような講義の他にも、課題研究として課題論文の提出や、考査(試験)も実施されます。
修了考査
正式に公認会計士と認められるための最後の関門が修了考査です。
論文式試験の合格、実務経験、実務補習所これらすべての要件を満たした人だけが受験することができます。
試験科目は、「監査」「会計」「税務」「経営・IT」「法規・職業倫理」の5つです。
記述式の試験で、特徴としては、論文式試験よりもより実務的な場面を想定した問題が多いことが挙げられます。
短答式試験や論文式試験と比べると合格はしやすい傾向があり、合格率は50%~70%となることが多いです。
年収・給与はどれくらい?

公認会計士とは専門性の高い難関資格ということもあり、一般平均よりも高い給与が見込めます。
厚生労働省が公開している職業ごとの賃金をまとめたデータ「賃金構造基本統計調査」では、例年600万円~1000万円ほどの年収額が報告されています(公認会計士と税理士をあわせた年収データ)。
同データによると、20代半ばの月額基本給与は25万円~35万円ほどで、年収にして500~650万円ほど。30代半ば~40代になれば、年収が1,000万円を超えることもあるようです。
また、公認会計士の資格を活かして外資系金融やコンサルティングファームなどに転職すれば、若くても年収1000万円以上は十分狙えます。
もちろん、就職先が大手か中小かというところで給与の差がでることはありますが、一般的な同世代の社会人と比較すると、公認会計士の給与は高い水準にあると言えるでしょう。
公認会計士とは難関資格である分、高額な給与を望めるということもあり、このような給与面の魅力が高い人気を集める理由の1つとなっています。
職種別年収ランキング
ここでは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査ではなく、人材会社大手マイナビが集計した職業別の年収ランキングを一部確認してみましょう。
こちらは、マイナビ転職に掲載された求人のモデル年収を基に算定されており、公認会計士は26位の662万円でした。
しかし、ランキング上位のコンサルタント(2位)やアセットマネージャー(3位)等で活躍する公認会計士は多く、やはり高い年収が期待できること間違いなしです。
| 順位 | 職種名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | システムアナリスト | 1,609万円 |
| 2 | コンサルタント(経営戦略) | 1,444万円 |
| 3 | アセットマネージャー | 1,100万円 |
| 4 | 情報アーキテクト・UI/UXデザイナー | 1,000万円 |
| 5 | ITアーキテクト | 975万円 |
| 6 | 不動産営業 | 952万円 |
| 7 | システムコンサルタント(業務系) | 932万円 |
| 8 | 金融営業(個人)・リテール・FP | 918万円 |
| 9 | 基礎研究 | 900万円 |
| 10 | 用地仕入 | 867万円 |
| ・・・ | ||
| 26 | 公認会計士 | 662万円 |
| ・・・ | ||
| 36 | 税理士 | 635万円 |
| ・・・ | ||
| 96 | 司法書士・行政書士 | 552万円 |
公認会計士の就職先と業務

先ほど、公認会計士とは企業の財務・会計に関する情報を第三者の立場からチェックする仕事だと説明しましたが、実は公認会計士の業務内容はそれだけではありません。
働く場所によって公認会計士の仕事は変わり、幅広い活躍の場があるのです。
ここからは、公認会計士の就職先とはどういったものがあるのか、また就職先に応じた業務内容を解説していきます。
メインとなるのは監査法人における「監査業務」
公認会計士の就職先として第一に挙げられるのは、「監査法人」です。
監査法人とは、企業の監査業務を行う専門的な法人組織を指します。日本国内には様々な監査法人がありますが、中でも「トーマツ」「あずさ」「EY新日本」「PwCあらた」という4つの監査法人はビック4(big4)と呼ばれ、最大手の組織として知られています。
監査法人で行われる業務とは、企業の作成した財務諸表を監査することがメインです。
企業の財務・会計データがまとめられた財務諸表は、銀行や投資家が融資・投資をするかどうかの判断基準になります。
財務諸表を改ざんして報告するいわゆる「粉飾決算」が行われれば、資本市場に大きな影響が及んでしまいます。
経済的に重要な意味を持つ財務諸表に間違いがないかをチェックし、企業の信用性を第三者の立場から調査するのが、公認会計士の重要な役割なのです。
この業務とは公認会計士だけに許された独占業務となっており、社会的・経済的に大きな意義のある仕事と言えるでしょう。
4月~6月を決算の時期としている企業が多いため、この3ヶ月が監査法人の繁忙期とされていますが、監査を担当する企業(クライアント)や担当の数に応じて忙しい時期が変わります。
また、大きな監査法人であれば大企業を相手にするため大人数のチームを組んで対応する機会が多い一方、中規模の監査法人は人数が少ないため幅広い業務を任される傾向にあります。
監査法人以外で働く選択肢
公認会計士の就職先とは、監査法人に限られません。どんな企業も財務状況を把握するには会計の知識が必要です。そのため、会計のプロである会計士が活躍できる場は一般企業にも幅広く存在するのです。
公認会計士が一般企業に就職する際には、
- コンサルティング会社で財務・経営に関するコンサルタント
- 一般企業の経理・財務を担う部署で経理業務や事業計画の立案
- 金融機関で投資や融資に関する業務
- ベンチャー企業で経理としてIPO(新規上場)のサポート
などの選択肢が挙げられます。
特に監査法人で経験を積んだ公認会計士は、企業会計・財務だけでなく経営に関しても知識を持っているため、様々な会社で重宝されます。
一般企業で財務の面から企業の事業戦略を考えたり、コンサルティング会社でM&Aや事業再生に関するコンサルティング業務など、財務の面から見た企業経営に関わる業務に就くケースが多く見られます。
また、ベンチャー企業でバックオフィスを担当するのも選択肢の1つ。ベンチャー企業はIPO(株式上)を考えていることも多く、企業会計の専門家が社内にいることは非常に心強いのです。
ベンチャー企業でバックオフィスリーダーとして勤務すれば、場合によってはCFOのポジションに就ける可能性もあり、バリバリ活躍したい方には興味深い選択肢と言えるでしょう。
その反面、実力主義で成果を出さなければいけないというプレッシャーもあることは忘れてはいけません。
経験を積んで独立という道もある
監査法人で経験を積んだ公認会計士の中には、独立開業をして自分の会計事務所を立ち上げる人も少なくありません。
個人で会計事務所を立ち上げた場合、業務内容は主に会計コンサルティングや税務業務が主になります。
税務業務とは、企業や個人事業主が毎年支払う税金(法人税)の申告業務のサポートをしたり、税務署類の作成を代行する業務です。
税務業務とは税理士資格がなければ行うことができませんが、公認会計士資格を持っていれば試験を受けることなく税理士資格を取得することが可能です。
独立開業をする公認会計士は、受けられる業務の幅を広げるために税理士資格を取得することが多いようです。
具体的な仕事内容とは

公認会計士の仕事とは多岐にわたるうえ、働く場所によっても異なりますが、主に「監査業務」「税務」「コンサルティング業務」の3つに分けることができます。
では、公認会計士の具体的な仕事内容について確認していきましょう。
公認会計士の仕事とは①:監査業務
公認会計士の仕事である監査業務とは、企業の財務諸表の適正性(内容に根拠があるかどうか、一定のルールに従って作成されているかなど)を公正な立場でチェックし、財務諸表の内容に誤りや虚偽、粉飾などがないことを証明することです。
上場企業や大企業などでは、法令によって監査を受けることが義務付けられており、本決算時だけでなく四半期ごとの決算も開示する義務があることから、公認会計士はその都度企業の監査を行います。
この監査業務とは公認会計士の独占業務であり、公正な態度を保つことや特定の利害を持たないことなど独立性が求められます。
それゆえに、使命感のある方に向いている仕事といえます。
公認会計士の仕事とは②:税務業務
税務業務とは、税理士の独占業務ですが、公認会計士も税理士登録をすることで税務業務を行うことができます。
公認会計士が税務業務を行うのは、監査法人に勤めているときよりも、独立開業した場合の方が多くなります。
というのも、独立した後は監査法人のように大きな監査業務を請け負うことが難しくなるため、中小企業を対象として監査から税務・コンサルティングなどをトータルで行うケースが多いです。
税務業務の具体的な内容は、後ほど「税理士との違いとは」で詳しく解説します。
公認会計士の仕事とは③:コンサルティング業務
コンサルティング業務とは公認会計士の独占業務ではありませんが、その豊富な知識を生かして企業をトータルでアシストする経営コンサルティング分野においても公認会計士が活躍しています。
コンサルティング業務とは、企業が抱える課題を解決するための相談に乗ったり、助言をしたりすることです。
公認会計士が携わるコンサルティング業務としては、会計コンサルティング、M&Aアドバイザリー業務、企業再生アドバイザリー業務などがありますが、会計コンサルティングがメインになるケースが多いです。
税理士との違いとは

公認会計士は、先ほど述べたように公認会計士資格を取得すれば試験を受けること無く「税理士資格」も取得することができます。
税理士とは、広く言えば公認会計士と同様に企業の会計に関する業務を行う職業です。
会計士と税理士とは同じような職業だと思っている方もいるかもしれませんが、実際のところ業務内容には大きな違いがあります。
ここでは、公認会計士と税理士の違いとはなにかを解説します。
税理士の仕事とは
税理士の仕事とは大きく3つに分けられており、「税務書類の作成」「税務代理」「税務に関する相談」が主になります。
税務書類の作成とは
企業や個人事業主が税務署に対して提出する書類の作成(確定申告書など)
税務代理とは
企業や個人事業主が、税務署に対して税金を申告する作業の代行。また、税務署からの税務調査に立ち会い、納税者に代わって対応すること。
税務に関する相談とは
企業や個人事業主の納税手続きや、納税額の計算などについてアドバイスをすること。また、節税の相談にのることもある。
公認会計士の独占業務が監査業務であるように、税理士の独占業務は税務業務とされています。
公認会計士は、税理士の資格を取得すれば上記の税理士独占業務も行うことが可能です。
公認会計士と税理士の試験の違い
公認会計士試験とは最難関の試験として有名ですが、一方の税理士試験も難易度の高い試験として知られています。
公認会計士と税理士試験の大きな違いは、受験資格と試験方式にあります。
公認会計士
年齢、性別、学歴に関わらず受験をすることができる。
試験は短答式試験と論文式試験の2段階に分かれており、所定の必須科目・選択科目を受験して全ての科目で合格点をとる必要がある。
短答式試験に合格した場合は合格後2年間短答式試験が免除される。
また、論文式試験に落ちた場合も、所定の成績を納めた場合には2年間特定の科目について受験免除となる。
論文式試験までの合格率は、例年10%ほど。
税理士
学歴や所持資格に応じて受験資格が定められている。
例)大学、短大、高等専門学校もしくは専修学校の専門課程を修了し、なおかつ法律学および経済学に属する科目を1つ以上取得している者など
試験は1回のみで、所定の必須科目・選択科目を受験し、各科目ごとに合否が出される。一度合格した科目は、その後ずっと合格の状態が続くため、年数をかけて受験をクリアする方法がとれる。
試験合格率は、例年10%~20%ほど。
このように、税理士試験は公認会計士とは違い、細かな受験資格が定められているものの合格までの難易度は多少低いです。
特に、税理士試験は各科目ごとで合否判定が出され、なおかつ合格の状態もずっと続くため、時間をかけて対策をすることができます。とはいえ、例年の合格率は10%~20%と低く、税理士試験も資格試験の中では非常に難易度が高い部類だと言えるでしょう。
AIによって将来無くなる職業ってホント!?
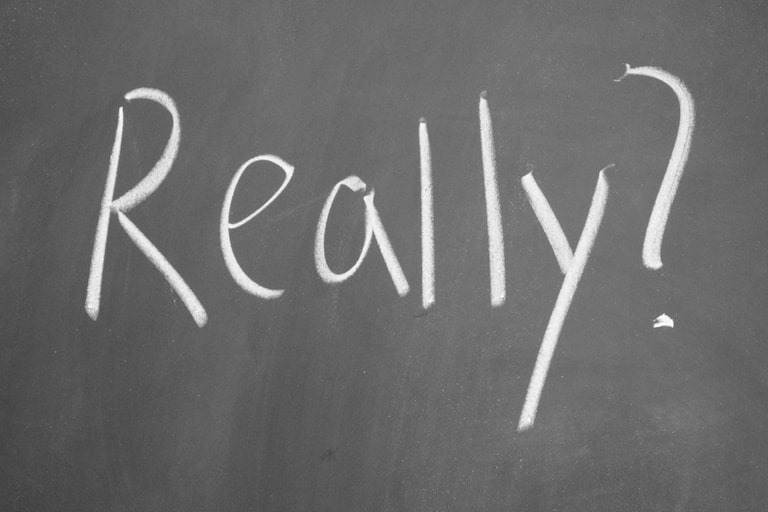
公認会計士を目指す人にとっては無視できないニュースとして2015年に注目されたのが、オックスフォード大学の論文で今後20年以内に「AIにより無くなる仕事」の第2位で公認会計士が選ばれたことです。
AIとは人工知能のことで、近年発達が著しい分野の1つです。
確かに、最近は同じような業務効率化としてRPAの導入も進んでおり、簡単な会計処理は自動化されているケースも増えており、経理スタッフの作業量は大きく減少しています。
それでは、このままだとAIによって公認会計士の仕事はなくなってしまうのか?
結論から言うと、「公認会計士の仕事は無くならない」と言えます。
実務では例外処理がつきもの
何故かと言うと、AIがいくら自己判断が行えるようになったとしても、例外処理は実務ではつきものです。
公認会計士の勉強をしていても、実務現場では教科書通りの手続きや仕訳ができないことは沢山あります。
ここまで柔軟にAIが行えるようになるのは、まだまだ先のことでしょう。
最終確認は人(公認会計士)が必要
AIが行った作業が正しいか判断するのは人間であり公認会計士でなければなりません。
業務はダブルチェックなど、人の作業を他の人が最終確認するように、AIが行った作業を確認し、最終判断を下すのもやはり人の手が必要です。
それには会計監査の専門である公認会計士の知識と経験が求められます。
公認会計士の将来と役割
実は監査法人ではAI技術を監査業務に導入しているケースは増えており、会計士のよる作業は機械に取って代わっていることは事実。
したがって、今後は単純な作業や事務処理等はAIをはじめとした作業は機械化されるでしょう。
それでも、例外処理や高度な判断、並びに最終判断を行うのは公認会計士の役割となります。
つまり、公認会計士とAIは共存しながら、質の高い会計監査を提供していく時代になるということです。
また、単純な作業は自動化されるということは、公認会計士にはより専門的で的確な判断が求められる時代になるとも言えるでしょう。
公認会計士とはのまとめ
ここでは「公認会計士とは」について簡単にまとめてきました。
公認会計士とはどんな資格で、年収や仕事について簡単にイメージがついたと思います。
資格試験制度や平均年収並びに仕事内容については他のページで詳しく解説しているので、そちらのページもぜひ参考にしてみてください。
公認会計士になって充実したキャリア形成を実現させましょう。