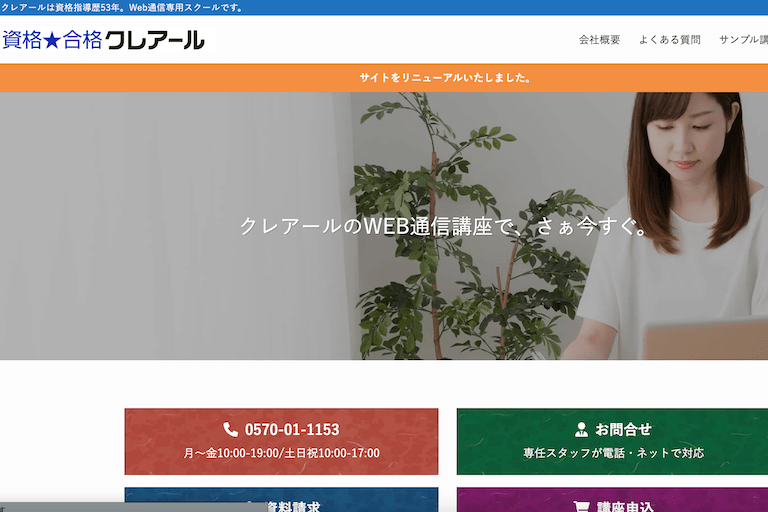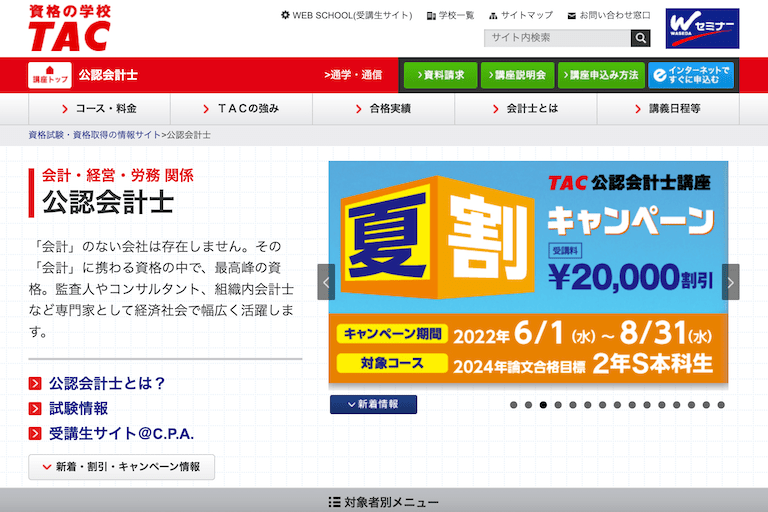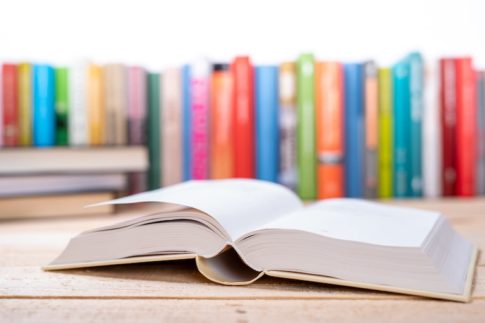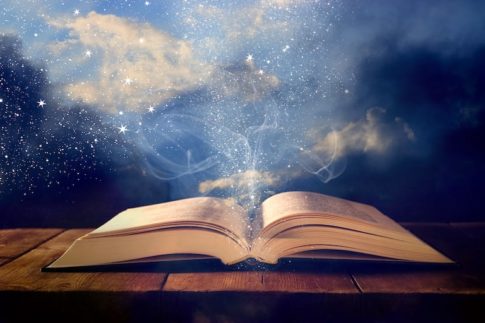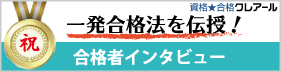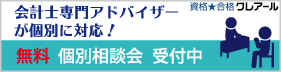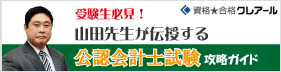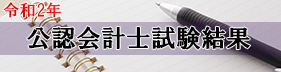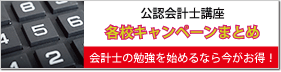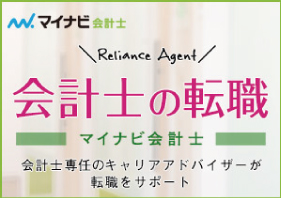公認会計士と大学について解説
公認会計士は高度な知識を必要とする専門性の高い国家資格であるため、活躍の場は広く高い年収も期待できます。
そんな公認会計士を目指す場合、大学卒業という学歴が必要でしょうか?
今回は公認会計士試験の受験資格や合格実績豊富な大学や会計大学院について詳しく紹介していきます。
公認会計士試験の受験資格に学歴は必要ない

公認会計士試験の受験資格に学歴・年齢・性別の制限はありません。
大学卒の人だけでなく、だれでも受験可能です。2020年度の公認会計士試験では最高齢合格者が61歳、最年少合格者は18歳でした。
過去には16歳の現役高校生が合格した例もあります。
旧試験制度では、大学卒業または旧1次試験合格などの受験資格がありましたが、2005年度以降の新試験移行後は誰でも公認会計士試験が受験できるようになっているのが特徴です。
合格後に大手監査法人を希望するなら大卒は重要
公認会計士試験では学歴は不問ですが、合格後の就職活動では少なからぬ影響をもたらします。
試験に合格した後は、一定期間、業務補助や実習補習などを行う必要があり、そのために監査法人(公認会計士の独占業務である会計監査を行う組織)で社員として働くのが一般的な流れです。
特に、監査法人のBIG4(あずさ監査法人、トーマツ監査法人、新日本監査法人、PwCあらた監査法人)のいずれかに就職を希望する場合は、ライバルは慶応や早稲田、東大などの難関大学卒業生がほとんど。
そんな中で高卒生はどうしても不利になりがちです。
大学時代だからこそ築ける人間関係や将来のキャリア形成を考慮すると、やはり大学を卒業することには意義があります。
難易度の高い公認会計士試験に強い大学は存在する

公認会計士試験は、医師国家試験・司法試験と並んで最難関国家試験といわれるほど難易度が高く、2020年度の公認会計士試験の合格率は10.1%と発表されています。
下表は公認会計士合格者数の多い大学をランキング形式で示したものですが、これを見るとトップ10を占めるのは偏差値上位の難関大学であることがわかります。
2021年度実施分の大学別合格者数ランキング
| 順位 | 大学名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾 | 178名 |
| 2位 | 早稲田 | 126名 |
| 3位 | 明治 | 72名 |
| 4位 | 中央 | 65名 |
| 5位 | 東京 | 58名 |
| 6位 | 立命館 | 49名 |
| 7位 | 京都 | 41名 |
| 8位 | 神戸 | 38名 |
| 9位 | 大阪 | 36名 |
| 10位 | 一橋 | 35名 |
【参考:公認会計士試験の状況 2021年度】
http://cpa-mitakai.net/keio_trans.html
最上位の慶應義塾は47年連続第1位を誇る公認会計士試験に圧倒的な強さを誇っています。
また、2位の早稲田も毎年100名以上の合格者を輩出しており、公認会計士試験といえば早慶が強いというイメージがあります。
おすすめの学部・学科はある?
公認会計士の試験は、必須科目が「財務会計論」「管理会計論」「監査論」「企業法」の4科目。選択科目が「経営学」「経済学」「統計学」「民法」から1科目です。
試験形式は必須科目が短答式(マークシート方式)で、選択科目が論文式の2段階になっています。
商学部の会計学科や経済学部を専攻しておけば、大学で勉強した知識を活かせるので、公認会計士試験の勉強を始める際はスムーズに取り掛かることができます。
とはいえ、実際には法学部や文学部、工学部など他学部を専攻している人も合格していますから、学部・学科に関係なく公認会計士になることは可能です。
高校生におすすめの大学はある?
高校生が公認会計士の資格取得を目指すためにおすすめの大学をご紹介します。いずれも公認会計士の合格率が比較的高く、資格取得に力を入れている大学です。
明治大学「経理研究所」
大学で公認会計士を目指すなら、明治大学という選択肢があります。
明治大学には、日本で最初に設立された公認会計士養成機関「国家試験指導センター経理研究所」があり、公認会計士試験に合格するための「特別会計研究室」や「会計士講座」などが設けられています。
講座は大学の授業と両立できるようスケジュールが組まれており、特別会計研究室に入室した人には奨学金を受けられるなどの特典もあります。
中央大学「多摩学生研究棟『炎の塔』」
中央大学にも「経理研究所」が設けられており、公認会計士論文式試験現役合格率51.6%という実績を誇っています。
また、多摩に「炎の塔」と呼ばれている学生研究棟があり、公認会計士や裁判官・検察官などの法曹資格といった難関資格取得を目指す学生のための学習施設があります。
日曜・祝日も朝8時から夜11時まで利用でき、難関試験合格に向けて学生同士がお互いに切磋琢磨しながら学習しています。
公認会計士試験合格者などからの指導も受けられるので、確実に実力をつけたい人におすすめです。
会計大学院(アカウンティングスクール)とは

弁護士など法律家を養成するための法科大学院(ロースクール)があるように、公認会計士にも会計大学院(アカウンティングスクール)が設置されている大学があります。
会計大学院へは、4年制を卒業して「学士」の学位を取得し、大学院の選考基準をクリアすれば入学することができます。
修業年数は2年。会計のプロフェッショナルを養成することを目的としており、現役の公認会計士が指導にあたるなど、実務に即した授業が行われます。
司法試験の場合はロースクールへの進学が受験資格になるルートもありますが、公認会計士の場合は受験資格に学歴は不要ですから、会計大学院に進学する理由や必要性はあるのでしょうか?
ここでは会計大学院とその必要性について見ていきましょう。
会計大学院が設置されている大学・専門学校
会計大学院は2005年に早稲田大学など10校を中心に設立されました。
やがて専門学校や民間企業も参入し、ピーク時には18校を数えるまでに。
しかし、リーマンショックの影響などもあり会計大学院へ進学する学生が減少し、それに伴って閉鎖する会計大学院も相次ぎ、現在は下記の12校となっています。
| 地域 | 設置校(大学院) | 専攻 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 大学院経済学研究科会計情報専攻 |
| 東北 | 東北 | 大学院経済学研究科会計専門職専攻 |
| 関東 | 早稲田 | 大学院会計研究科専攻 |
| 明治 | 専門職大学院会計専門職研究科会計専門職専攻 | |
| 青山学院 | 大学院会計プロフェッショナル研究科会計プロフェッション専攻 | |
| 千葉商科 | 大学院会計ファイナンス研究科 | |
| LEC東京 リーガルマインド大学院 |
高度専門職研究科会計専門職専攻 | |
| 大原大学院 | 大学院会計ファイナンス研究科 | |
| 近畿 | 関西学院 | 専門職大学院経営戦略研究科会計専門職専攻 |
| 関西 | 大学院会計研究科会計人養成専攻 | |
| 兵庫県立 | 大学院会計研究科会計専門職専攻 | |
| 九州 | 熊本学園 | 大学院会計専門職研究科アカウンティング専攻 |
会計大学院を修了すると試験科目が免除される
先述したように、公認会計士試験には必須科目が4科目あります。
会計大学院には免除制度が設けられており、2年の修業期間中に定められた単位を取得して「専門職修士」の学位を与えられると、短答式試験の3科目が免除され、受験するのは「企業法」の1科目だけで済みます。
「企業法」は短答式の中でも点数を稼ぎやすい科目。
会計大学院を修了すれば短答式試験の合格は約束されたも同然で、その後に控えている論文式試験の勉強に集中することができます。
ただし、注意を要するのは、会計大学院を修了するまでの2年間は免除制度は適用されないこと。
公認会計士試験の勉強時間は3,500時間が目安といわれ、1日5時間として2年ほどの勉強で合格を果たす人がいます。
つまり、大学在学中からみっちり勉強すれば、会計大学院を修了する前に合格を果たすことが十分可能ということになります。
会計大学院だけの勉強では合格できない
会計大学院では高度な専門知識を習得することは可能ですが、公認会計士試験に特化した授業は行っていないため、最短合格を目指すなら大原学園やTACといった資格予備校で受講する必要があります。
しかし、資格予備校にも通うとなれば学費はかなり高額になります。
東北大学など国公立大学にある会計大学院でも2年間の学費は130万円前後、私立大学なら350万円前後かかります。
大原学園の公認会計士集中資格取得コースの場合は、1年5か月分で110万円前後です。両方を合計すると安く見積もっても約240万円。
会計大学院修了で受けられる特典が試験科目の免除だけなら、会計大学院に通う必要性は感じられないという人も少なくないでしょう。
合格者の多くは大卒
会計大学院での勉強だけでは公認会計士試験に合格できないこともあり、多くの合格者は大学在籍中か卒業後に資格予備校を利用していました。
下表は2022年度の学歴別合格者のデータを一部抜粋したものですが、合格者構成の割合を見ると現役大学生と卒業生が大半を占めています。
会計大学院の必要性が高ければ合格者の数値はもっと上がっていたでしょうし、会計大学院そのものが東京大学や京都大学など最高学府に設置されていたはずです。
| 区分 | 合格者 | 合格者構成 |
|---|---|---|
| 会計大学院修了 | 22名 | 1.5% |
| 会計大学院在学 | 14名 | 1.0% |
| 大学卒業 | 632名 | 43.4% |
| 大学在学 | 642名 | 44.1% |
学歴が関係ない試験なのに会計大学院へ進学すべき?

先述のとおり公認会計士試験の受験資格に学歴・年齢・性別の制限はなく、公認会計士試験受験のためには会計大学院へ進学する必要はありません。
では、会計士大学院へ進学するメリットはどのようなものがあるでしょうか?
会計大学院に進学するメリット
実務的な知識・技能を身に着けられる
会計大学院では、アカデミックかつ実務的な会計や経営に関する知識や技能を得ることができます。
研究者である教授のもとで学術的な講義を受けることができるほか、実務家の方の講義もあるため、実務家の視点から「理論的にはこうだが、実務ではこうする」といった話を聞くことのできます。
このように公認会計士試験の勉強だけでは得られない実務的な知識を深めていくことができる点は、会計大学院の大きなメリットの一つです。
こうした専門的な教育を受けた実績は、公認会計士となった後でも価値を認められるでしょう。
人脈ができる
2つ目のメリットは、会計業界での人脈を構築できる点です。会計大学院には大手監査法人で公認会計士として働く同級生のほか、大手上場企業の経理・経営企画部門、コンサルティング会社、銀行などの金融機関など、多くの業界で活躍する同級生がいます。
会計業界は狭い業界であり、実際に仕事関係で同級生に遭遇することも少なくありません。
また、このような横のつながりに加えて、会計士大学院には、講師として会計研究者や実務家などが招かれており専門的な経験や知見を持つ人との縦のつながりも作ることができます。
このような人脈を幅広くもっておくことは将来のキャリアプランを描くうえで、非常に大きな財産となることは間違いありません。
学歴が得られる
会計大学院を修了することで、「大学院修了」という学歴が得られるのもメリットのひとつです。
大学院卒業の肩書は、公認会計士としてのキャリアやその後の転職や独立を踏まえると、特に時間や費用に余裕のある方にとってはメリットがあるといえるでしょう。
会計大学院への進学がおすすめの人
次のような人は会計士大学院への進学がおすすめといえるでしょう。
- 学術的、実務的な知識を身に着けたい
- 人脈を広げたい
- 大学院卒の学歴が欲しい
- 時間や費用に余裕がある
まとめ
公認会計士試験の受験資格に大学卒業等の学歴は存在しておらず、誰でも受験可能です。
しかし、試験合格後の監査法人への就職活動や、その後のキャリアアップを図るうえで、大卒という学歴が有利に働くことは確かです。
会計士大学院(アカウンティングスクール)も公認会計士試験に合格するための1つの方法として候補にあがりますが、学費や免除制度を踏まえると費用対効果はそこまで期待できないかもしれません。
事実、公認会計士試験の合格者の多くは大卒レベルの最終学歴が圧倒的に多いうえに、海外のように修士号を取得してもそこまで評価は上がるとは言えない状況です。
その一方で、会計士大学院には学術的・実務的な知識が身に着けられる、人脈を広げられるなどの一定のメリットはあります。
そのため時間や学費を支払う余裕があり、こういったメリットに魅力を感じる人にとっては会計大学院への進学も考えられる選択肢の一つと言えるでしょう。