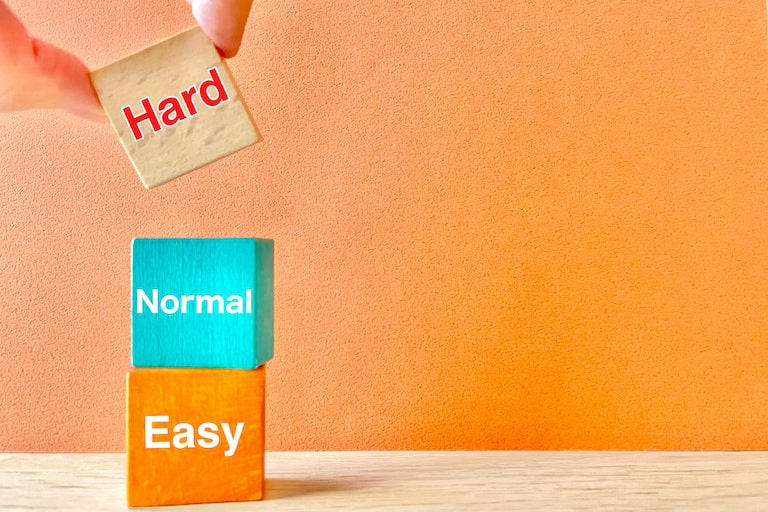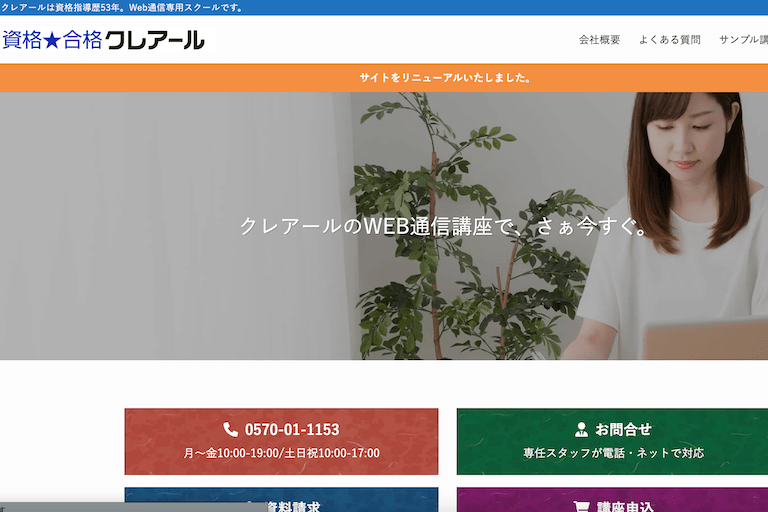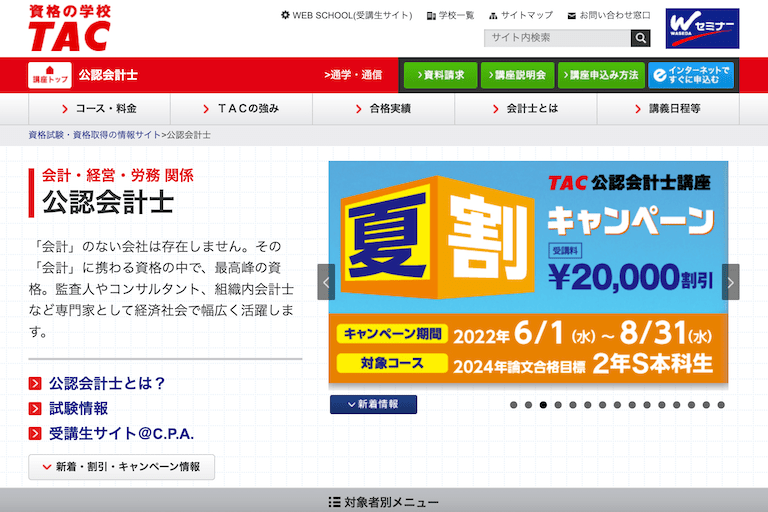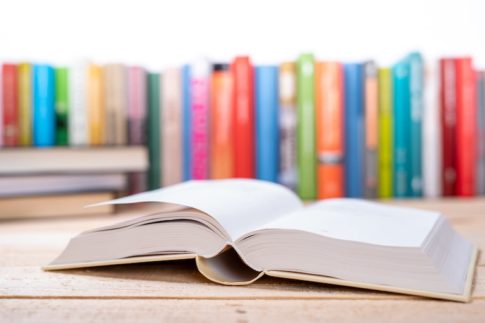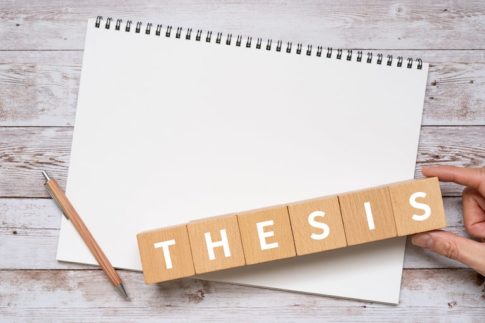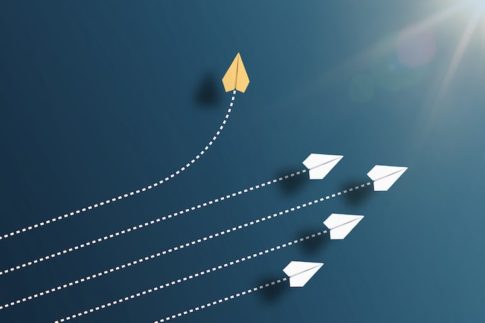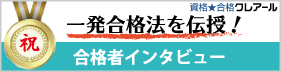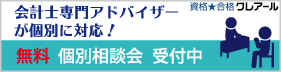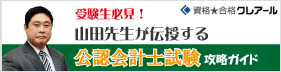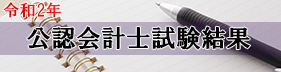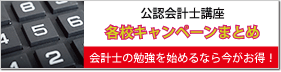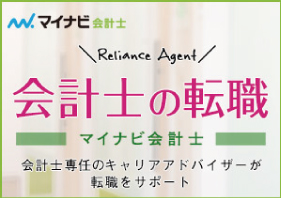公認会計士試験は難易度が非常に高いことで有名で、合格まで長期間を要する人も少なくありません。
しかしながら、実際に公認会計士試験の難易度を把握している方は多くないでしょう。
- 「公認会計士試験って実際どれくらい難しいの?」
- 「公認会計士試験はどのくらい勉強すれば合格できるの?」
などといった公認会計士試験の難易度について気になる方向けに、合格率や必要となる勉強時間などの観点から詳しく解説します。
また、公認会計士が目指す価値がある資格なのかや税理士試験との難易度の比較についても解説させて頂きます。
 |
山田 和宗 2010年公認会計士登録 大手監査法人で国内上場企業を中心とした監査業務に4年間従事 2011年には山田和宗公認会計士事務所開業 会計教育を中心に活躍しており、クレアールでは簿記を担当 |
公認会計士試験の難易度は高い?

公認会計士試験は試験範囲も膨大で、難易度も高く、合格するのは簡単ではありません。
こちらでは、公認会計士試験の合格に必要な勉強時間と年数について解説します。
必要な勉強時間は?
公認会計士試験は医者や弁護士とともに三大難関国家試験にも数えられる非常に難易度の高い試験です。
公認会計士試験合格者の勉強時間は2,000時間~5,000時間の範囲に収まるのが一般的と言われており、他の資格試験と比較しても長い勉強時間が必要なことが分かるかと思います。
試験合格者のなかでも勉強時間にかなりの幅がありますが、これは受験回数によっても勉強時間が大きく異なってくるためです。
最短一発の試験で合格できると比較的少ない勉強時間ですませることができますが、ストレートで合格できる人は多くはありません。
2回や3回と受験を重ねる人も多くおり、その場合に勉強時間が多くなる傾向にあります。
これらの事情を考慮すると、平均して合格レベルに達するのに必要な勉強時間はおよそ3,500時間~4,000時間が目安と言われています。
これから公認会計士を目指そうか迷っている方は場合によっては、それよりも多くかかることを覚悟しておいたほうがよいでしょう。
合格まで何年かかる?
独学ではなく、tac、大原、CPA会計学院、クレアールなどの資格予備校のもとで勉強を進める場合、公認会計士試験対策講座の最も一般的なコースは2年での合格を目指すカリキュラムとなっています。
しかしながら、先にも触れたとおり2年で一発合格できる方は多くはありません。
難易度が非常に高い試験のため、勉強期間2年で1発合格できる方は少数で、多くの方は2回~3回以上受験して合格する傾向にあります。
直近3年間の公認会計士試験合格者・合格率推移
直近の公認会計士試験の合格者数と合格率の推移は下表のとおりです。
| 年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 願書提出者数 | 13,231 | 14,192 | 18,789 |
| 短答式試験受験者数 | 11,598 | 12,260 | 16,701 |
| 短答式合格者数 | 1,861 | 2,060 | 1,979 |
| 論文式試験受験者数 | 3,719 | 3,992 | 4,067 |
| 最終合格者数 | 1,335 | 1,360 | 1,456 |
| 合格率 | 10.1% | 9.6% | 7.7% |
例年の最終合格者は1,300人~1,400人前後、合格率は10%前後で推移しています。
他の資格試験と比較しても合格率は低く、難易度の高さが見て取ることができます。
また、最終合格者数は直近3年間で増加傾向にはありますが、願書提出者(受験者数)がそれ以上に大きく増加したため、2022年試験では合格率は7%台にまで低下する結果となっています。
このデータが示すとおり、公認会計士業界としては人手不足の状態にもあり最終合格者数は少しずつ増えている状況ではありますが、それ以上に受験希望者が増加しているため、合格難易度は数年前と比べると高くなっている傾向があります。
年齢別合格者数(2022年)
直近の2022年公認会計士試験の年齢別合格者数とその構成比は下表のとおりです。
| 区分 | 願書提出者数(名) | 合格者数(名) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 402 | 21 | 1.4% |
| 20歳以上25歳未満 | 8,906 | 929 | 63.8% |
| 25歳以上30歳未満 | 4,183 | 337 | 23.1% |
| 30歳以上35歳未満 | 2,144 | 117 | 8.0% |
| 35歳以上40歳未満 | 1,239 | 26 | 1.8% |
| 40歳以上45歳未満 | 752 | 19 | 1.3% |
| 45歳以上50歳未満 | 473 | 5 | 0.3% |
| 50歳以上55歳未満 | 288 | 1 | 0.1% |
| 55歳以上60歳未満 | 191 | 1 | 0.1% |
| 60歳以上65歳未満 | 108 | 0 | 0.0% |
| 65歳以上 | 103 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 18,789 | 1,456 | 100% |
(注)合格者構成比の合計欄の値は、端数処理の関係で各区分の合計と必ずしも一致しない。
最も構成比が大きいのは20歳以上25歳未満の年代層で、全合格者のうち63.8%も占めています。
次に多いのは25歳以上30歳未満で23.1%を占めており、20歳以上25歳未満と足し合わせると86.9%にも達し、ほとんどの合格者が20歳代を占めている状況です。
20歳代の合格者が大半となっている理由は大きく2つあります。
一つ目は、大学在学中や大学卒業後に資格浪人をして合格を目指している受験生が多いという点です。
また、もう一つの理由は、20歳代の受験者の合格率が高いという点です。
文系の大学生や資格浪人生は、社会人と比べるとまとまって勉強時間を確保しやすいことが多く、多くの勉強時間を必要とする公認会計士試験を目指しやすく、勉強に集中しできる分、合格率も全体の合格率7.7%よりも2-3%程高い結果となっているのです。
学歴別合格者数(2022年)
直近の2022年公認会計士試験の学歴別合格者数とその構成比は下表のとおりです。
| 区分 | 願書提出者数(名) | 合格者数(名) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 大学院修了 | 961 | 39 | 2.7% |
| 会計専門職大学院修了 | 690 | 22 | 1.5% |
| 大学院在学 | 143 | 13 | 0.9% |
| 会計専門職大学院在学 | 165 | 14 | 1.0% |
| 大学卒業(短大含む) | 7,923 | 632 | 43.4% |
| 大学在学(短大在学含む) | 6,559 | 642 | 44.1% |
| 高校卒業 | 1,899 | 76 | 5.2% |
| その他 | 449 | 18 | 1.2% |
| 合計 | 18,789 | 1,456 | 100% |
(注)合格者構成比の合計欄の値は、端数処理の関係で各区分の合計と必ずしも一致しない。
試験合格者数のうち、最も大きな構成比を占めるのは大学在学中の区分で、44.1%を占めています。
続いて大学卒業の区分が43.4%となっています。
この2つの区分で全体の87.5%を占めており、合格者の大半が大学在学中もしくは大卒の人という結果になっています。
大学在学/大卒以外では、高校卒業の区分が次いで大きく5.1%となっています。
先述のとおり、大学在学中や大学卒業後に資格浪人をして合格を目指している受験生は多く、大学在学中と大学卒業の区分での構成比が大きくなっています。
また、願書提出者数では、大学卒業の区分が大学在学の区分を上回っているのに対し、合格者数では大学卒業の区分の方が少なくなっております。
この逆転現象は、大学在学生の受験者は社会人と比べるとまとまって勉強時間を確保しやすいことが多く、勉強に集中しできる分、合格率も大学卒業の区分の方や他の区分等と比べ高くなっていることによるものです。
社会人でも公認会計士は目指せるか

先述のとおり、年代別・学歴別の合格者構成をみると20代前半の大学生や資格浪人生の合格者数が多く、合格率も高くなっていることが推測できます。
では、勉強時間も限られている社会人が公認会計士を目指すのは無謀な選択なのでしょうか。
社会人が公認会計士を目指すことは簡単ではありませんが、全く不可能な話でもありません。
実際のところ、公認会計士試験は社会人経験者での合格者も例年一定数存在しています。
しかしながら、社会人が勉強と仕事を両立する場合には、公認会計士試験合格者に最も大きな構成を占める大学生と比べると1日当たりの勉強時間が短くなってしまうのは避けられない側面はあるでしょう。
そのため、社会人が公認会計士を目指す場合には長期スパンでの学習計画を立てることをおすすめします。
試験合格までの期間と勉強時間
社会人の方が公認会計士試験合格を目指す場合、休職・退職でもしない限り、毎日まとまった勉強時間を確保するのは困難でしょう。
もし、社会人の方が平日3時間、土日5時間の勉強を一日も欠かさず継続した場合でも、合格者平均の勉強時間3,500時間~4,000時間に達するには、2.7年~3年ほどかかる計算になります。
そのため、働きながら公認会計士を目指す場合には、3年超のスパンで長期での学習計画を立てることをおすすめします。
一方で、実際の社会人合格者のなかでは、学習初期は働きながら仕事と勉強を両立させ、試験の1年前~直前期ごろにかけて、勉強に専念することで2年~3年程の短期間で合格している方もいらっしゃいます。
また、経理の実務経験者や日商簿記1級や簿記2級などを既に保有している方は一定のアドバンテージもあるため、スムーズに勉強を開始できるでしょう。
社会人の方が公認会計士試験合格を目指す場合、ご自身が確保できる勉強時間や仕事の休職・退職の可否や基礎知識の有無等を勘案しながら、3年ほどの勉強期間をベースにスケジュールを検討することをおすすめします。
社会人が目指す場合のメリット
- (受験専念できる場合)まとまった勉強時間を確保できる。
- 実務経験があり、会計・監査をイメージしやすい場合がある。
社会人の方でも、受験に専念することができる場合、まとまった勉強時間を確保できるのは大きなメリットでしょう。
また、社会人経験があることで、会計・監査の実際のイメージがわきやすく、学習効率が上がる点もメリットの一つといえます。
社会人が目指す場合のデメリット
- (受験専念できない場合)勉強時間を確保を確保しにくい。
公認会計士試験は試験範囲も広範で勉強時間も多く必要となるため、短期合格のためには、まとまった勉強時間の確保は非常に重要な要素の一つとなります。
その点、仕事と勉強を両立させる場合、1日当たりの勉強時間は少なくなってしまうため、比較的長期間の学習計画をたてる必要がある点はデメリットとなります。
試験難易度が高い理由
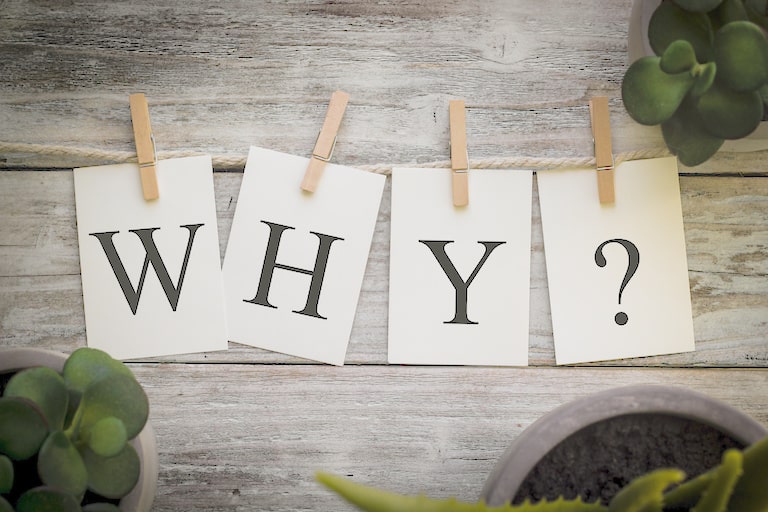
試験科目が多い
公認会計士試験の難易度が高い理由として、試験科目が多いうえに各科目の学習範囲も膨大なことがあげられます。
公認会計士の試験科目は、財務会計、管理会計、監査論、企業法、租税法、選択1科目で構成。
どれも専門性が高く難易度が高いので、効率よく学習できたとしても豊富な学習時間の確保が必要となります。
1日10時間ほど勉強時間を確保しても、2年から3年かけて合格する人が多いくらい難易度は高めです。
一発合格を目指して対策が必要
公認会計士試験は、試験科目が多いうえに一発合格を見据えて対策しないといけないのが難易度を高めている理由の1つでもあります。
税理士資格であれば、恒久的な科目合格が認められているため、1科目ずつ勉強して合格が目指せます。
一方、公認会計士試験は短答式合格、および論文式の科目合格で2年間の試験免除が認められていますが、2年以内に論文式試験で最終合格できなければ、また短答式から再スタートになってしまいます。
したがって、特に学習時間の確保が困難な社会人にとっては、公認会計士は難易度が高い試験となります。
合格者数が決められている
公認会計士試験では、下記のように合格の基準点が決められています。
短答式試験 総点数の70%を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率。ただし、1科目につき、その満点の40%に満たないものがある場合は不合格となることがある。論文式試験総点数の60%を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率。ただし、1科目につき、その満点の40%に満たないものがある場合は、不合格となることがある。
しかし、合格者数を一定水準に維持するため、仮に受験生の出来が良い場合は、合格基準が上げられてしまうのです。
つまり、短答式試験で総点数70%を取っていても、合格者数を絞るために75%以上に上げられることがあります。
逆も当然考えられ、70%基準だと合格者が少ない場合は、67%など基準点を下げたことも今までに多くありました。
※令和2年第1回目の短答式試験の基準点は57%でした。
したがって、公認会計士試験は絶対評価ではなく、相対評価の試験であることを理解しておきましょう。
修了考査の難易度は低い?
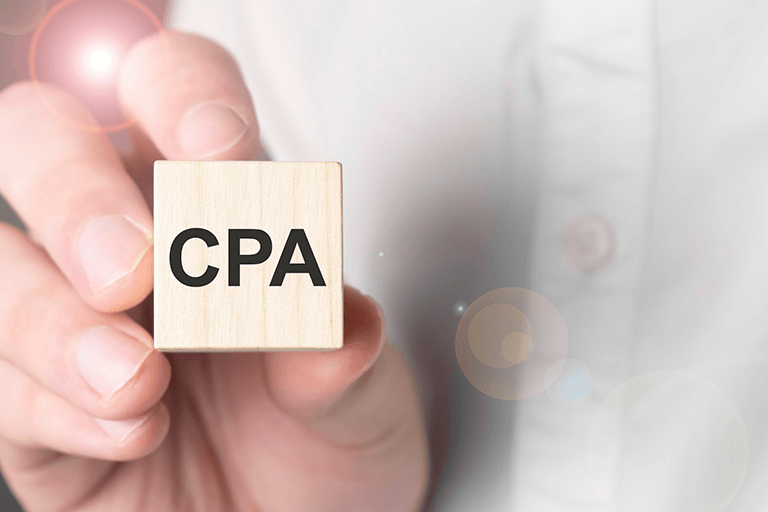
修了考査とは
修了考査とは、公認会計士の資格を取るために必要な最後の関門です。
公認会計士の資格を取得するには、公認会計士試験に合格するだけでは公認会計士にはなれないのです。
公認会計士となるには、公認会計士試験(短答式試験と論文式試験)に合格した後に、一定年数の実務経験を積む必要があります。
また、その他にも、実務補習所という公認会計士試験合格者が通う研修機関に通い所定の単位の取得が求められます。
この実務経験と実務補習所の単位取得を満たした公認会計士試験合格者が最後の関門として受ける試験が修了考査なのです。
修了考査は、一定の実務経験等も積んだ公認会計士試験合格者が、公認会計士として業務を行ううえで、基礎となる知識や思考力等を図る非常に重要な試験です。
以下では、修了考査の概要や直近の合格率や難易度について詳しく解説していきます。
修了考査の実施概要
修了考査の実施概要は下表のとおりです。
| 試験日程 | 例年12月中旬の土日2日間 |
|---|---|
| 試験会場 | 東京(3会場) 大阪(1会場) 愛知(1会場) 福岡(1会場) |
| 試験科目 | 「監査に関する理論及び実務」 「会計に関する理論及び実務」 「税に関する理論及び実務」 「経営に関する理論及び実務(コンピュータに関する理論を含む)」 「公認会計士の業務に関する法規・職業倫理」 の5科目 |
| 試験時間/配点 | 監査:3時間/300点 会計:3時間/300点 税務:3時間/300点 経営・IT:2時間/200点 職業倫理:1時間/100点 |
| 合格基準 | 合格基準は、総点数の60%を基準として、修了考査運営委員会が相当と認めた得点比率。 ただし、満点の 40%に満たない科目が1科目でもある者は、不合格となることがある。 |
| 合格発表 | 例年4月上旬 (2023年度試験の合格発表は2024年4月5日を予定) |
修了考査の試験は、例年12月中旬の土日2日間に渡って実施され、例年4月上旬に合格発表がなされます。
試験会場は東京、大阪、愛知、福岡の全5会場(東京のみ3会場で実施予定※2023年)となっています。
試験科目は、「監査に関する理論及び実務」「会計に関する理論及び実務」「税務に関する理論及び実務」「経営に関する理論及び実務(コンピュータに関する理論を含む)」「公認会計士の業務に関する法規・職業倫理」の5科目で、科目別の配点は「監査」・「会計」・「税務」が300点、「経営」が200点、「職業倫理」が100点となっています。
合格基準は、総点数の 60%を基準として修了考査運営委員会が相当と認めた得点比率とされていますが、満点の40%に満たない科目が1科目でもあると足切りとなり、不合格とされる場合があります。
修了考査の直近合格率【6年分】
修了考査の直近6年の合格率推移は下表のとおりです。
| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 願書提出者数 | 1,653人 | 1,618人 | 1,896人 | 2,126人 | 2,366人 | 2,181人 |
| 受験者数 | 1,536人 | 1,495人 | 1,749人 | 1,936人 | 2,174人 | 2,000人 |
| 合格数 | 1,065人 | 838人 | 854人 | 959人 | 1,404人 | 1,392人 |
| 対受験者数合格率 | 69.3% | 56.1% | 48.8% | 49.5% | 64.6% | 69.6% |
直近6年間の修了考査合格率はおよそ50%~70%程度の範囲で推移しており、大体受験者の2人に1人か3人に1人が不合格となる計算です。
合格率からみてわかるとおり、公認会計士の本試験(短答式試験、論文式試験)と比べると合格率も高くなっています。
公認会計士は目指すだけの価値があるのか

公認会計士試験合格には、平均して3,500時間~4,000時間もの長時間の勉強が必要です。
また、論文式試験合格後も実務経験や修了考査の合格など資格取得までの道のりは長いです。
このような難関国家資格である公認会計士を目指す価値はあるのでしょうか。
公認会計士を目指すメリットをご紹介します。
平均年収が高い
公認会計士の平均年収は一般の会社員と比較しても高い水準にあります。
厚生労働省『賃金構造基本調査』(令和2年)では公認会計士・税理士の平均年収は、958万4,200円とされており、労働者の平均年収は478万2,900円と比較しても高い水準と言えるでしょう。
学歴が問われない
公認会計士の業界は、一般企業に比べて学歴が重要視されない傾向にあります。
大手の監査法人でも、偏差値の高くない大学卒の方や高卒の方も多くいます。
昇進や昇格においても、学歴が考慮されることは一般にないといってもよいでしょう。
また、独立開業する選択肢もあり、自分自身の努力と能力次第でキャリアを積めるため、学歴に自信のない方にもおすすめできる資格といえます。
将来のキャリアの幅・選択肢が広い
公認会計士は会計監査を独占業務としており、監査法人に勤め会計監査業務を行っている人が最も多いですが、公認会計士ができる業務は幅広く存在します。
会計監査以外の業務の例としては、会計アドバイザリー(コンサル)や会計書類の記帳代行・助言、組織再編(M&A)、企業再生、株式公開(IPO)、IFRS導入、デューデリジェンスなどに関連する会計業務などがあります。
その他にも、公認会計士資格を有していれば、試験を受験することなく税理士登録も可能ですので、税理士として税務関連業務を実施する人もいます。
また、日本にとどまらず海外への道も拓けておりアメリカや欧州など幅広く活躍できる場が用意されています。
税理士試験との難易度を比較

公認会計士と税理士の合格率推移
公認会計士試験と税理士試験の合格率推移は下表のとおりです。
| 公認会計士 | 税理士 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 11.1% | 15.3% |
| 2019年度 | 10.7% | 18.1% |
| 2020年度 | 10.1% | 20.3% |
| 2021年度 | 9.6% | 18.8% |
| 2022年度 | 7.7% | 19.5% |
公認会計士試験の方が難しい?
税理士試験は公認会計士試験と同じくらい難易度の高い試験と言われています。
公認会計士試験の合格率は10%前後で推移しているのに対し、税理士試験の合格率は18%前後となっており、公認会計士と比べると、税理士の方が合格率が高い結果となっています。
合格率をみると税理士の方が合格難易度が低いようにみえますが、これは、税理士試験が科目合格制度を取っており、全科目合格者だけではなく科目合格者も含めて合格率が計算されていることによるものです。
そのため、合格率だけをみて公認会計士試験の方が税理士よりも難しいとは言い切ることはできず、実際のところ、個人の向き不向きによって変わるというのが実態でしょう。
【まとめ】公認会計士試験の難しい理由は学習量の多さ

公認会計士試験は1次試験(短答式試験)と2次試験(論文式試験)の2段階に分かれており、1次試験に合格した人だけが2次試験を受けることができる仕組みになっています。(1次試験は年2回、2次試験は年1回しか開催されません。)
試験範囲が広く、3500時間~4000時間程度の膨大な勉強時間が必要だといわれています。
難関試験であるがゆえ、1回で1次・2次両方とも合格できる人もいれば、複数回挑戦してようやく2次試験まで合格することができる人もいるのです。
つまり、少ない受験回数で合格できる人ほど、合格までに要した勉強時間も少なくて済むわけです。
短答式試験で4科目、論文式試験で実質6科目が課される上に、すべての科目の範囲が膨大なのです。
本記事では、公認会計士の難易度について気になる方向けに、合格率や必要となる勉強時間などの観点から詳しく解説しました。
また、公認会計士が目指す価値がある資格なのかや税理士試験との難易度の比較についても触れさせて頂きました。
公認会計士試験は医師や弁護士とともに三大難関国家試験にも数えられる非常に難易度の高い試験ですが、医師や弁護士にも負けず劣らずの、見合った価値のある強い資格といえます。
以上、公認会計士に興味のある方に向けた公認会計士試験に関する解説でした。