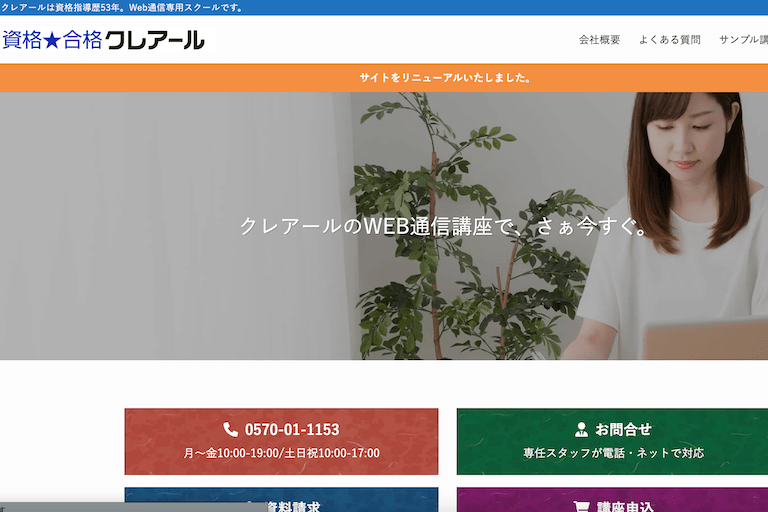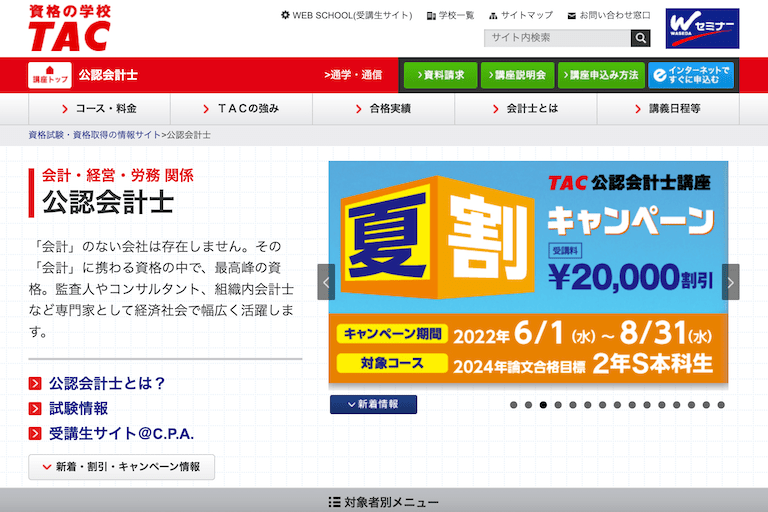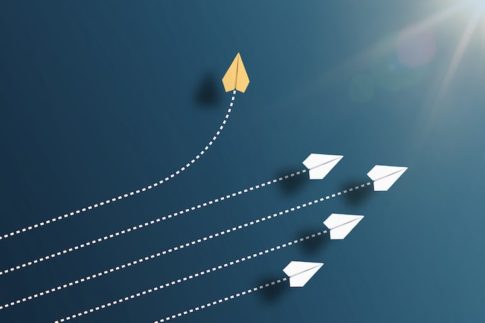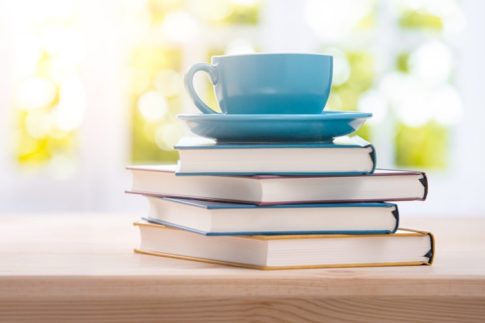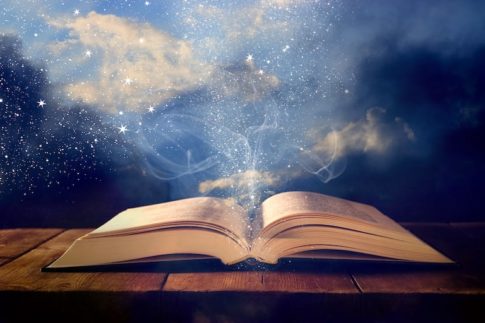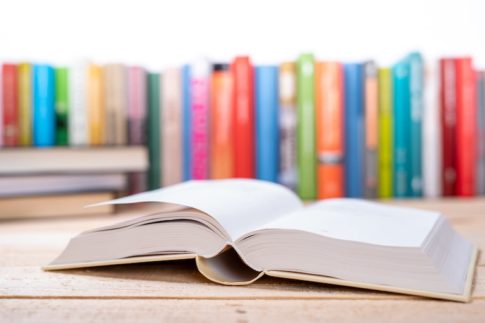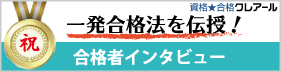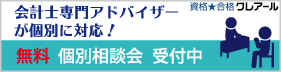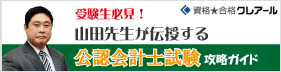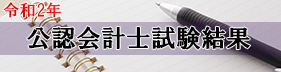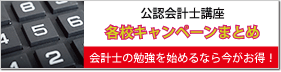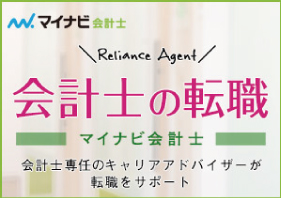公認会計士の資格は修了考査に合格することで、取得することができます。
一般に公認会計士試験と呼ばれる試験を合格するだけでは「公認会計士試験合格者」であり、「公認会計士」を名乗ることはできないのです。
本記事では、公認会計士試験合格から資格取得に至るまでの道のりを解説します。
また、最後の関門である修了考査の試験内容や合格率などについても詳しく解説していきたいと思います。
公認会計士の修了考査とは
公認会計士の修了考査とは、公認会計士の資格を取るために必要な最後の関門です。
公認会計士の資格を取得するには、公認会計士試験に合格するだけでは公認会計士にはなれないのです。
公認会計士となるには、公認会計士試験(短答式試験と論文式試験)に合格した後に、一定年数の実務経験を積む必要があります。
また、その他にも、実務補習所という公認会計士試験合格者が通う研修期間に通い所定の単位の取得が求められます。
この実務経験と実務補習所の単位取得を満たした公認会計士試験合格者が最後の関門として受ける試験が修了考査なのです。
修了考査は、一定の実務経験等も積んだ公認会計士候補者が、公認会計士として業務を行ううえで、基礎となる知識や思考力等を図る非常に重要な試験です。
論文式試験合格後から公認会計士登録までの流れとともに、修了考査の内容や難易度について詳しく解説していきます。
論文式試験合格後~公認会計士登録までの流れ

公認会計士になるために必要な要件
論文式試験合格者が公認会計士になるために必要な要件を整理すると以下の通りです。
- 修了考査に合格する(短答式試験及び論文式試験)
- 2年間の実務経験を積む
- 実務補習所に3年間通い、所定の単位を取得する
以上の3つが公認会計士になる人が満たすべき要件です。
修了考査についての解説は後ほど詳しく解説しますが、実務経験と実務補習所とは具体的にどのような要件なのでしょうか。
これから詳しく解説していきます。
実務経験とは~監査法人・企業で2年間(※)実務経験を積む~
公認会計士資格を取得するには、監査法人や企業で2年間(※)実務経験を積む必要があります。
実務経験を積むためには、大きく2つの方法があります。「業務補助」もしくは「実務従事」です。
業務補助とは、公認会計士又は監査法人の監査証明業務に携わり、その補助の役割を果たすことです。
ほとんどの論文式試験合格者は、監査法人に就職し実際に監査証明業務に携わることで、この要件を満たしています。
実務従事は事業会社等に常勤として勤務し、なおかつ、その業務内容が法令で定められた業務として認められた場合に、この要件を満たすことができます。
法令で定められた業務の代表的なものを挙げると銀行や保険会社における「貸付や債務保証などの資金の運用に関する事務」や一般事業会社における「原価計算など財務分析に関する事務」などがあります。
なお、この実務経験は、多くの受験生が論文式試験合格後に実務経験の要件を満たしていますが、論文式試験前に実務経験を積むことも認められています。
実務補習所とは~指定の補習所で3年間講義を受ける~
公認会計士資格を取得するには、実務補習所で原則として3年間の実務補習をうけ、所定の単位を取得する必要があります。
実務補習所に聞き馴染みがない人がほとんどかと思いますが、論文式試験合格者が実務経験を積みながら通う塾・予備校とイメージして頂ければ問題ありません。
講義形式は、ライブ講義のほかe-learnning、ディスカッションなどがあり、宿泊合宿なども実施されます。
このよな講義の他にも、課題研究として課題論文の提出や、考査(試験)も実施されます。
修了考査の試験内容や難易度

論文式試験合格後に、一定の実務経験と実務補習所の所定の単位を満たすことで、修了考査を受験することができます。
では、公認会計士資格の最後の関門である修了考査の試験内容や難易度はどのようなものなのでしょうか。
これから詳しく解説していきます。
修了考査の試験内容
修了考査の試験科目は、「監査」「会計」「税務」「経営・IT」「法規・職業倫理」の5つです。
試験日程は、例年12月2週目の土日に2日間に渡って実施され、4月上旬に合格発表がなされています。
記述式の試験で、出題範囲は広く問題のボリュームも多いです。
試験問題の特徴としては、論文式試験よりも、より実務的な場面を想定した問題が多いことが挙げられます。
そのため理論的な内容は勿論のこととして、実務上での取り扱いなどを知っておく必要があります。
修了考査の合格率推移
修了考査の合格率は論文式試験と比較するとかなり高いです。
合格率は、論文式試験が約30~35%となることが多いのに対し、修了考査は約50%~70%となっています。
令和1年度以降、受験者数・合格者数ともに増加傾向が続いていますが、直近の令和3年度試験(2022年4月8日合格発表)では合格者数が大幅に増加し、合格率も前年の令和2年度(2020年度)から15%以上高い64.6%となりました。
なお、令和1年度(2019年度)と令和2年度(2020年度)は過去からみても異例ともいわれるほど合格率が低かった年であり、それ以前は、60%~70%の合格率となることがほとんどでした。
| 年度 | 平成30年度 (2018年度) |
令和1年度 (2019年度) |
令和2年度 (2020年度) |
令和3年度 (2021年度) |
|---|---|---|---|---|
| 願書提出者数 | 1,618人 | 1,896人 | 2,126人 | 2,366人 |
| 受験者数 | 1,495人 | 1,749人 | 1,936人 | 2,174人 |
| 合格数 | 838人 | 854人 | 959人 | 1,404人 |
| 対受験者数合格率 | 56.1% | 48.8% | 49.5% | 64.6% |
合格者はどんな対策してる?勉強時間は?
修了考査受験者のほとんどが資格予備校の修了考査対策講座を受講しています。
大手の資格予備校であるTACや大原、CPA学院等では修了考査対策として質の高いテキストや答練が作成されているため、対策講座に沿って勉強を進めることで修了考査の対策を行うことができます。
資格予備校に通わない場合、論文式試験と同様に市販のテキスト・教材はほとんどないため、非常に効率が悪くなってしまうというのが実情です。
勉強に費やす時間・期間は、合格者のなかでもかなり幅が広いです。
監査法人勤務の場合、試験休暇が14日程度与えられるため、有給休暇と併せて3~4週間ほど試験勉強期間を設け、その期間でみっちり勉強するという人も多いです。
いつ勉強を開始するかの時期も人により様々で、早い人では1年以上前から勉強を開始していますが、遅い人では試験の2週間前からという人もいます。
なお、一般に修了考査対策は監査法人に就職している人が有利といわれています。
なぜなら、修了考査はより実務的な内容の問題が出題されることを紹介しましたが、監査法人に勤めていれば会計監査業務の実務を経験できるので、実務面での基礎的な知識に優位性があることが多いからです。
また、それ以外にも、監査法人であれば試験休暇として2週間程度の休暇を取得できたりするのに対し、一般企業では終了考査に対する理解がないことも少なくなく、勉強時間の確保の面で監査法人勤務の方が有利な立場となることも多いのです。
それに加え、受験費用や資格予備校の講座料なども監査法人であれば負担してくれるところも多いです。
修了考査に失敗した場合はどうなる?
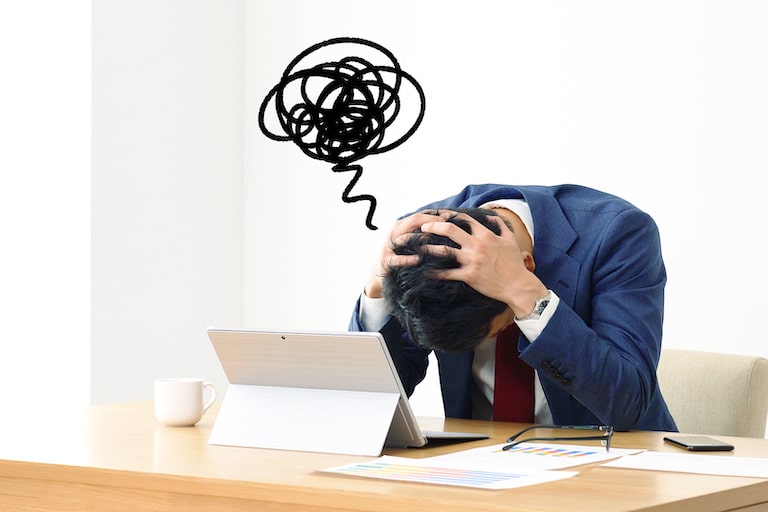
修了考査の合格率は、令和1年度と令和2年度試験では50%を下回っていますので、受験者の半数以上が不合格となることもありえます。
修了考査受験後に合否結果発表まで、落ちたらどうしようと不安な気持ちを抱える方も多いですが、修了考査は一度受験資格を得られれば、何度でも受験することができるため、気にしすぎる必要もないでしょう。
また、実務的な面でも、監査法人内では公認会計士資格がないとできない業務というのが、明確にある訳でもないので大きな支障はないともいえるでしょう。
しかしながら、監査法人に勤めている場合、法人によっては合格が遅れることで昇格が遅れてしまう等のリスクがないとはいえません。
近年、大手監査法人では、受験生に対し勉強の進捗を確認したり、業務日程を調整して勉強時間を確保するなど、積極的に法人内の修了考査合格率を挙げるために、働きかけている傾向もあるので、スムーズに合格できるよう、早めに試験対策を進めることをおすすめします。
まとめ
本記事では、公認会計士試験合格から資格取得に至るまでの道のりを解説しました。
また、公認会計士資格の最後の関門である修了考査の試験内容や合格率などについても詳しく解説しました。
論文式試験試験合格後にも、修了考査の合格のほか、一定の実務経験と実務補習所で所定の単位を満たす必要があることを説明しました。
修了考査については、合格率は論文式試験と比べると高いものの、試験範囲は広く問題ボリュームもあるため、資格予備校等で専用の対策講座を受講する人がほとんどであることを紹介させて頂きました。
公認会計士資格取得を目指す方や公認会計士に興味をお持ちの方に有意義な情報となれば幸いです。