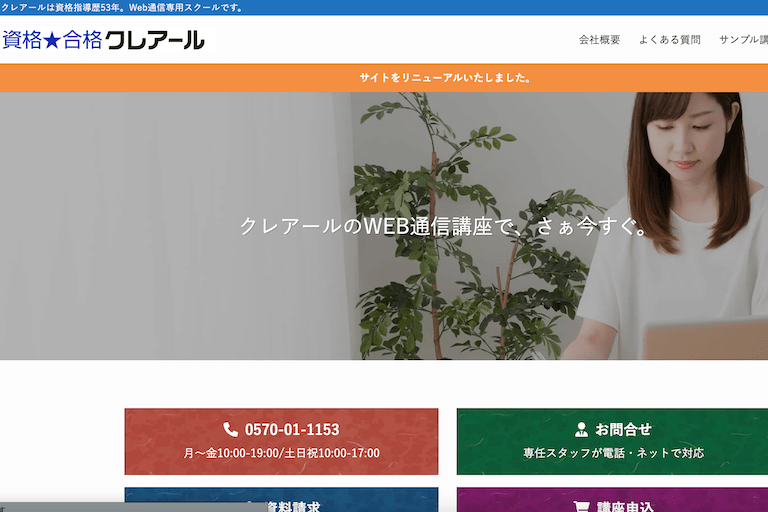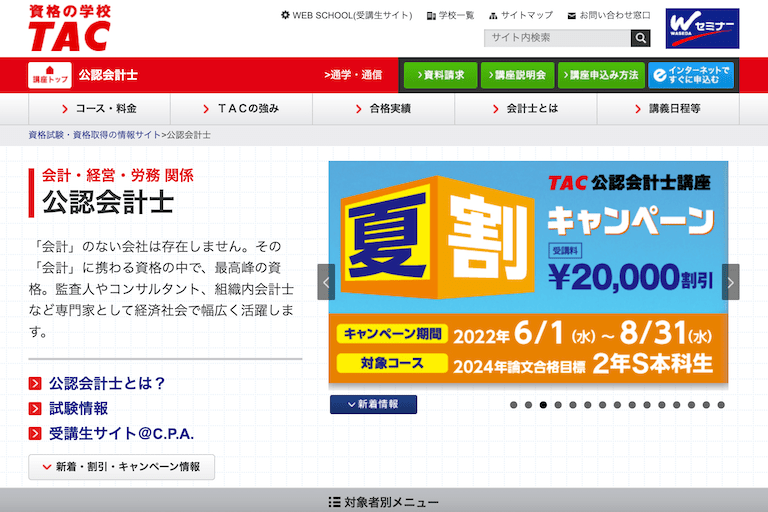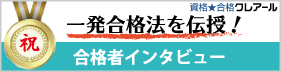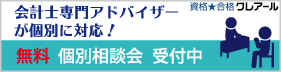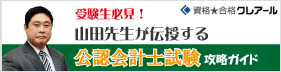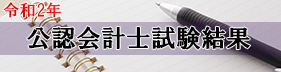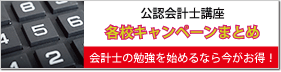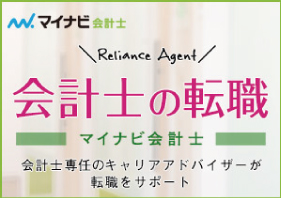資格が必要な「士業」の1つである公認会計士は、資格を取得しただけでは公認会計士の名称を使うことができません。日本公認会計士協会に登録申請をし、審査を通ってはじめて名乗ることができます。
ここでは、公認会計士試験の種類や受けられる優遇措置、試験に合格してから登録するまでにしなければならないことについて、わかりやすく解説していきます。
公認会計士の受験資格は?
医師・弁護士と並んで日本の三大国家資格といわれる公認会計士。
国家試験の中でも公認会計士試験は超難関ですが、受験資格に特に定めはなく、年齢、学歴、性別、国籍を問わず、だれでも受けることができます。
医師の国家試験は大学の医学部卒業、弁護士なら法科大学院課程修了というように学歴が受験資格とされていますが、公認会計士の場合は2006年に試験制度が一新され、受験資格に関する制限はなくなりました。
そのため、高校生から社会人まで幅広い層の人が受験しています。
2019年度の公認会計士試験の合格者は、最年少が18歳で最年長が62歳、平均年齢が25.2歳でした(参考:「令和元年公認会計士試験の合格発表の概要について」)。
受験から合格まで

公認会計士試験は、金融庁所属の「公認会計士・監査審査会(以下、審査会と略)」が実施しています。
試験は「短答式試験」と「論文式試験」の2段階選抜となっており、試合にたとえると短答式試験は予選、論文式試験は決戦にあたります。
短答式試験の試験科目・日程
短答式試験は、「企業法」「管理会計論」「監査論」「財務会計論(簿記1級と財務諸表)」の4科目で、いずれもマークシート方式による択一式試験です。
配点は財務会計論が200点、あとの3科目は各100点で計500点。合否は4科目の総合点で判定され、総合点数の70%が合格基準とされています。
ただし、1科目でも満点の40%に満たないものがあるときは不合格となり、再挑戦するときは全科目受け直さなければなりません。
短答式試験は第Ⅰ回と第Ⅱ回があり、1回目が12月(合格発表は翌1月)、2回目が翌年の5月(合格発表は6月)。
どちらかに合格すれば論文式試験を受けることができます。
論文式試験の試験科目・日程
試験科目は、「会計学」「監査論」「租税法」「企業法」「選択科目(経営学、経済学、民法、統計学から1科目)」の5科目。
会計学の配点が300点と高く、あとの4科目は各100点で計700点。合格基準は52%の得点比率とされています。
得点比率は偏差値のようなもので、受験生の平均を少し上回る程度で合格が可能です。この場合も、満点の40%に満たない科目があるときは不合格となります。
論文式試験の日程は8月の1回限りです。
試験は金・土・日の3日間に渡って実施され、合格発表は約3か月後。合格者には2週間以内に公認会計士試験合格証書が送られてきます。
| 注意 |
|---|
| 新型コロナウイルス感染症拡大状況を踏まえて、 令和3年度は短答式試験が1回のみの実施と変更されました。 |
| •短答式の試験期日:令和3年5月23日(日)、合格発表:同年6月18日(金) |
| •論文式の試験期日:令和3年8月20日(金)~22日(日)、合格発表:同年11月~12月 |
合格猶予や科目免除の制度がある
審査会では、学生・社会人を問わず多様な人たちが公認会計士の試験を受けやすいよう、次のような制度を設けています。
短答式試験の合格猶予期間
短答式試験に一度合格すると、以後2年間は申請によって短答試験が免除されることになっています。
もし、この後に受ける論文式試験で不合格になった場合、翌年と翌々年に限り、短答式試験を受けずに直接論文式試験に再チャレンジすることができます。
有資格者に対する科目免除制度
特定の資格を持つ人を対象とした免除制度も設けられています。
短答式試験の科目免除
次の①~④のいずれかに該当する人は、短答式試験の一部科目または全科目が免除されます。
- ①免除科目【財務会計論】
- 税理士の資格を持つ人。または税理士試験で簿記論や財務諸表論など指定科目について基準以上の成績を収めた人
- ②免除科目【財務会計論・管理会計論・監査論】
- 会計専門職大学で規定の科目を履修し、修士の学位を授与された人
- ③免除科目【財務会計論】
- 国・地方公共団体や大企業で会計または監査に関する実務経験が、通算7年以上ある人
- ④免除科目【全科目】
- 司法試験の合格者
論文式試験の科目免除
次の①~③に該当する人は、論文式試験の一部科目が免除となります。
- ①免除科目【租税法】
- 税理士の資格を持つ人
- ②免除科目【経済学または民法】
- 不動産鑑定士試験の合格者
- ③免除科目【企業法および民法】
- 司法試験の合格者
そのほかにも優遇措置が講じられているので、詳しくは「公認会計士・監査審査会」のwebサイトでご確認ください。
監査法人への入社後

論文式試験に合格すればすぐに公認会計士を名乗ることができるかというと、そうではありません。
日本公認会計士協会の「公認会計士名簿」への登録が必要で、そのためには「業務補助(2年間)」「実務補習(3年間)」「修了考査」の3つの要件を満たさなければなりません。
業務補助は実際に公認会計士の仕事を経験することで、合格者のほとんどは「監査法人」に就職して登録要件を満たしています。
就職してから公認会計士名簿に登録するまでの流れを見ていきましょう。
監査法人で実務経験を積む
監査法人とは、5人以上の公認会計士で設立され、公認会計士の独占業務である会計監査を行う組織のこと。
監査法人がクライアントの企業が作成した財務諸表(決算書)を検証し、適正であることを証明することによって投資家は安心してその企業の株を購入できるというわけです。
公認会計士の卵は監査法人の社員として働くことになります。
勤務地は、上場企業が集中する東京、名古屋、大阪、福岡など都市部にある大手監査法人が多いのですが、日本国内に限らず、米国や中国など日系企業の多い国の監査法人に就職する人もいます。
業務補助と実務補習は同時進行する
監査法人で働くことが2年間の「業務補助」の要件を満たすことになります。
それと同時進行で「実務補習」を行いますが、これは実務補習所に3年間通って実務を学び、一定の単位を取得します。
監査法人で働きながら週1~2回、平日の夜か土日に講義を受けるのが一般的なパターンです。
通う時間がない人には自宅でeラーニングを受講する方法もあります。
修了考査は最後のハードル
3年目に実務補習の修了考査(試験)を受けることになります。
試験は「監査」「会計」「税務」「経営・コンピュータ」「法規・職業倫理」の5科目で、2日間に渡って実施されます。
合格率は60%と比較的高く、論文式試験より合格しやすい試験です。
公認会計士の登録

修了考査に合格するといよいよ登録です。
登録申請をする前に登録免許税(60,000円)を税務署か金融機関で納付し、その領収証書を用意しておきます。
提出書類は住民票など役所で入手するものと、金融庁や法務局で入手する書類の計17種類あります。
その一部は日本公認会計士協会のweb上で必要事項を入力し、 PDFファイルを作成して印刷します。
書類がそろったら登録免許税の領収証書(原本)を添付して日本公認会計士協会へ簡易書留で郵送します
書類が審査を通ると公認会計士名簿に登録され、官報に公告されます。
本人には登録年月日と登録番号が通知され、その日から晴れて公認会計士の名称を使用することができます。
公認会計士の資格を取得したあとは、監査法人で仕事を継続する、一般企業に就職する、企業の海外支社に出向する、経営コンサルタントを目指して独立するなど、幅広いフィールドで活躍することができます。
【まとめ】受験資格がなく誰もがプロフェッショナルになれる
公認会計士は年齢・学歴不問なので、中卒や高卒でも試験に合格して登録すれば会計のプロフェッショナルとして活躍することができます。
実際に中卒で合格した人がいます。
しかし、公認会計士の試験は出題範囲が広く、専門的な知識を問われるものが多いため、合格するのに2~3年の勉強時間が必要といわれます。
独学で短期合格はまず不可能なので、資格の予備校や専門学校で効率よく確実に実力をつけることをおすすめします。
公認会計士コースがある予備校や専門学校は全国に数多くありますが、何よりも合格実績が豊富なところを選ぶことが大切です。
ここでは全国展開している学校と通信講座専門の予備校を紹介しますので一度検討してみてください。
| 資格の学校 TAC(タック) |
|---|
|
TACは北海道から九州まで全国26校舎展開しており、スケールメリットを得られるのが強みです。 たとえば、TACのテキストにない難問が出た場合でも、受験生の多くをTAC生が占めるため、自分だけでなくほかの受験生も正答できないので結果的に大きな差は生まれません。 TACの公認会計士コースで学習したことをしっかり押さえておけば合格ボーダーを越えることができます。 |
| 資格の大原 |
|---|
|
大原学園は北海道から沖縄まで全国83校展開しています。公認会計士の集中資格取得コースは担任制で、「その日の授業はその日のうちに理解する」を合言葉に、講師が一人ひとりの理解度・習熟度に応じて弱点強化の指導を行います。 スランプに陥ったときはメンタル面での相談にも乗ってもらえるので安心。専門学校の大原学園は学割や通学定期を利用できる点もメリットです。 |
| 働きながら学べるクレアール |
|---|
|
クレアールの通信講座は、会社の経理部や金融機関などで働きながら公認会計士の資格取得を目指す人に多く利用されています。 特長は、公認会計士試験で落としてはならない重要論点のみに絞った無駄のないテキストを用いていること。 十分な勉強時間がとれなくても講義の受講と復習がきちんとできる学習プランになっているので、自分のスケジュールに合わせて着実に力をつけていくことができます。 |