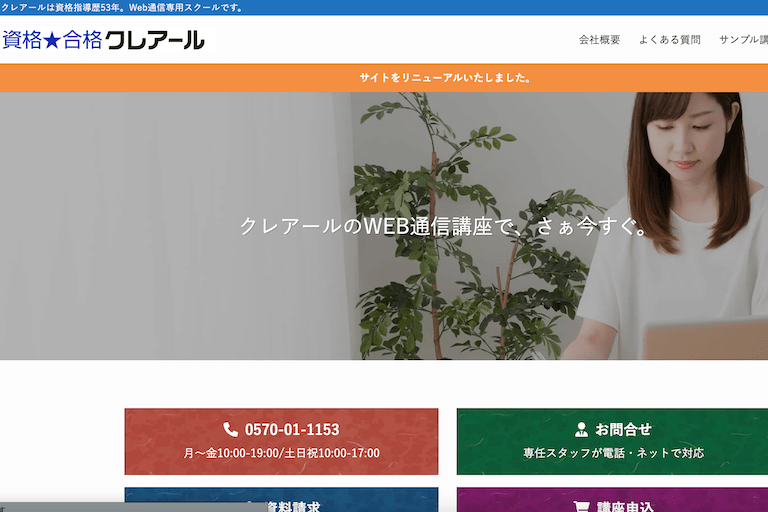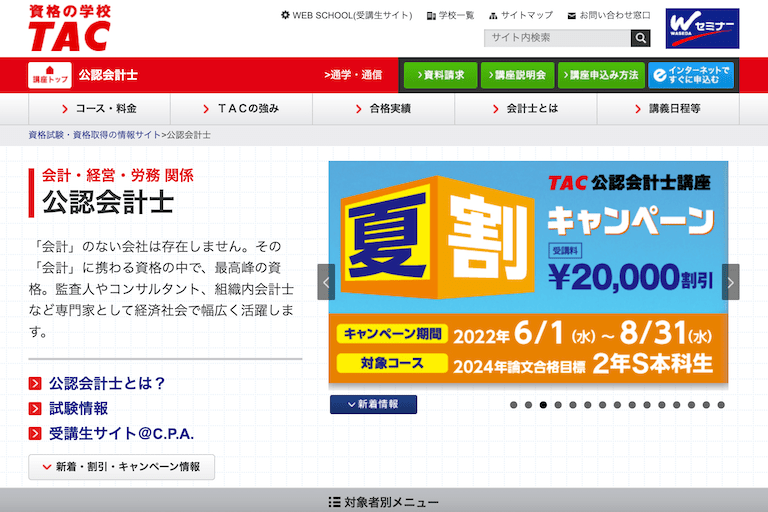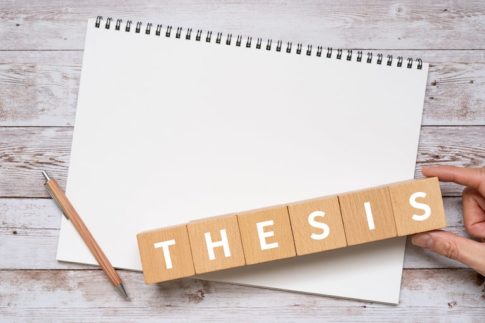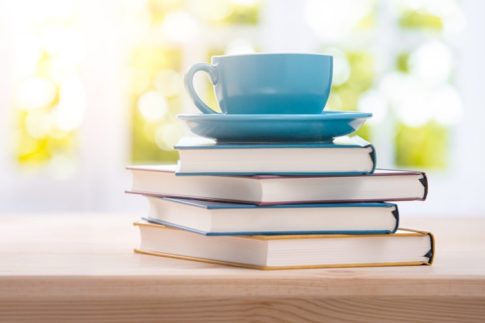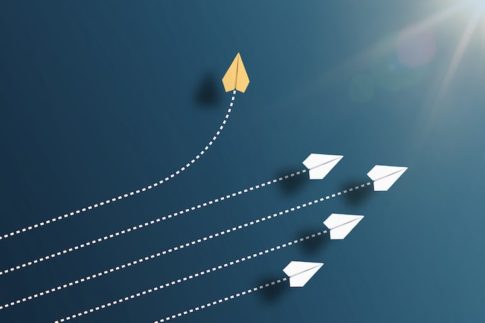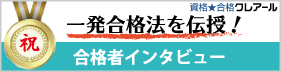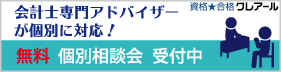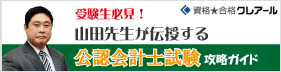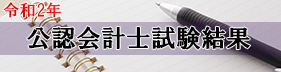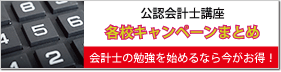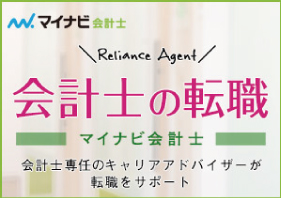公認会計士試験は試験範囲も膨大で難易度も高い試験です。
ただ漫然と勉強をするだけでは、公認会計士試験の合格を近づけることは難しいでしょう。
公認会計士試験の合格を目指すには、各科目のポイントをしっかり押さえ効率的に勉強を進める必要があります。
そこで、本記事では公認会計士試験の科目別の押さえるべきポイントを解説させて頂きます。
公認会計士試験の科目別の勉強法をしっかりと理解して試験合格目指して頑張りましょう。
公認会計士試験は範囲が膨大で難易度も高い

公認会計士試験は3大難関国家試験にも数えられる非常に難易度の高い試験です。
合格レベルに達するのに必要な勉強時間は平均3,500時間~4,000時間、期間にして約2-4年かかると言われています。
なぜ、公認会計士試験の合格にはこれほどの勉強期間が必要となるのでしょうか。
試験範囲が膨大
公認会計士試験の試験は、「財務会計」、「管理会計」、「監査論」、「租税法(法人税、消費税ほか)」、「企業法」、「経営学/民法/統計学など」など幅広い試験科目を受験する必要があります。
必然的に勉強範囲は膨大となり、資格予備校等で配布されるテキストだけでも優に50冊を超える分量となることもあります。
そのため、資格予備校等で公認会計士講座を受け、ただ、テキストの内容を理解するだけでも大変な時間が必要となります。
それに加え、講座の復習や答練などで知識の定着・アウトプットの訓練が必要となり、勉強を得意とする要領の良い人でも、長い勉強期間が必要となってしまうのです。
試験の難易度が高い
公認会計士試験の試験は非常に難易度が高く、合格するには幅広い能力が要求されます。
公認会計士試験は2段階形式の試験となっており、それぞれの試験で要求される能力も異なるため、試験の性質に応じて対策していく必要があります。
マーク形式の短答式試験では、限られた試験時間のなかで、膨大な問題文から必要な情報を取捨選択して、瞬時に処理する情報処理能力や広範な知識量などが問われます。
一方で、短答式試験合格後の論文式試験では、解答を論理的に説明する論理構成力や会計学・監査論等の基礎理論に対する深い理解などが必要となります。
このように、短答式試験と論文試験では試験性質の違いから、必要な対策も異なってくるため、それぞれの試験に応じた勉強が求められます。
その結果として、公認会計士試験(短答式+論文式)の難易度は高く、合格率はおよそ10%前後と低い合格率となっています。
短答式試験の勉強法
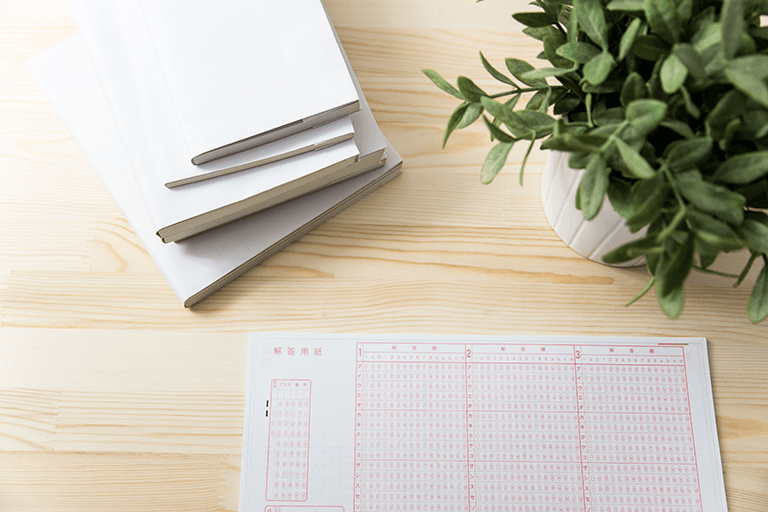
公認会計士試験の短答式試験は、マークシート形式であるがゆえに試験範囲も広く、暗記しなければならない事項も多いです。
また、問題量に対し与えられる試験時間も少ないため、限られた時間のなかで問題の趣旨を瞬時に理解し、解答を探し出す瞬発力や処理能力が試されます。
このため、効率よく勉強を進めるためには、試験科目別の出題傾向や対策方法を練って勉強計画を策定することが必要となります。
ここでは、公認会計士試験の短答式試験の科目別の勉強方法について解説します。
財務会計論
財務会計論は、簿記・財務諸表論の知識を試す科目です。
公認会計士業務の基礎ともいえる試験科目のため、短答式試験のみならず、公認会計士試験を通じて最も重要な科目といえるでしょう。
短答式試験においても、他の試験科目は試験時間60分、配点100点であるのに対し、財務会計論は試験時間120分、配点200点と、2倍の配点となっており最も優先して勉強すべき科目であるのがわかると思います。
対策方法としては、財務会計論は反復学習がものをいう科目です。
試験における配点も高く、最も重要度の高い科目であるため、勉強の初期段階から基礎問題を何度も繰り返し解き、頭と身体に基本を叩き込みましょう。
また、財務会計論は、計算問題である簿記と理論問題の財務諸表論の2つに分かれます。
しかしながら、これらは全く異なる内容ではなく、むしろ共通する内容のため簿記で会計処理を学んで財務諸表論で理論を学び落とし込む形で、同時並行的に学習するのが効率的といわれています。
こうすることで、会計処理や計算問題の背景にある会計理論を一体として理解することができ知識の定着率が良くなるため、並行して勉強することをおすすめしています。
管理会計論
管理会計論は、経営者の意思決定に用いられる管理会計及び原価計算の知識を試す試験科目です。
管理会計論は、財務会計論と同様に計算問題が中心に出題される試験科目であり、難易度や試験範囲も広く財務会計論の次に優先して学習すべき科目でしょう。
おすすめの対策法は、理論問題をしっかりと押さえることです。
計算問題は出題のバリエーションが広く、年度によっては複雑な難問も出題されることがあり、予想が立てずらい分野です。
一方で、管理会計論の理論問題は、配点の3-5割程度を占めますが、多くの理論問題は原価計算基準という基準から出題されます。
この原価計算基準は、全30P程度と分量も多くなく、比較的簡単に対策することができます。
そのため、原価計算基準を中心に理論問題をしっかりと押さえ、ベースとなる得点源を確保したうえで、計算問題を学習するという勉強方法をおすすめします。
監査論
監査論は公認会計士の独占業務である財務諸表監査の実務や理論の知識を試す試験科目です。
理論問題が中心ですが、試験範囲としては膨大で、全ての問題を完璧に対策することは難しい科目です。
また、ほとんどの受験生にとっては監査や会計の実務経験などがなく、学習内容のイメージが難しい科目でもあります。
おすすめの対策方法は、答練や過去問を繰り返し解き続けることです。
監査論では、tac・大原・CPA学院など予備校の講座やテキストで理論を一通り頭にインプットしたら、答練等の問題を繰り返し解くことで効率的な学習ができるでしょう。
繰り返し問題を解くことで出題頻度の高い典型論点については着実に得点できるようにし、合格ラインを確保したうえで、他の科目に勉強時間を割り振ることをおすすめします。
企業法
企業法は、会社法をメインとして、その他金融商品取引法や商法の知識を試す試験科目です。
理論問題が中心であり、試験範囲はある程度限られているものの、覚える内容が多く、法律条文を読むことや暗記が苦手な方にとっては難しい科目です。
一方で、試験範囲はある程度絞られていることから対策を立てやすい試験科目でもあり、得点源ともなりうる科目です。
そこで勉強方法としては、とにかく知識を頭に入れていく必要があるため、やはり、問題集や模試や答練を繰り返し解き、わからない部分があればテキストで調べる勉強法がおすすめです。
人によって向き不向きはあるかもしれませんが、比較的対策しやすい科目で安定した得点源にできる科目でもあるため、財務諸表論、管理会計論の次に優先して勉強することをおすすめします。
論文式試験の勉強法
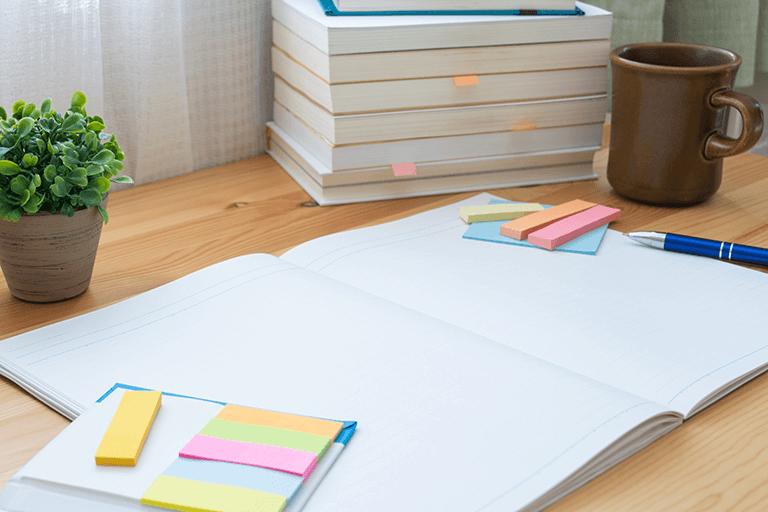
公認会計士試験の論文式試験では、解答を論理的に説明する論理構成力や試験科目の基礎理論に対する深い理解などが必要となります。
短答式試験とは異なり論述形式の試験になるため、答練や模試を活用して知識のアウトプットの練習にしっかりと取り組みましょう。
会計学
財務諸表論の理論中心に対策を進めましょう。
論文式試験は短答式試験とは異なり、解答を自ら作成する必要があります。
論述には単なる暗記に留まらない、基礎理論や背景に関する理解が必要となるため、テキストをしっかりと読み込むことをおすすめします。
計算問題は短答式試験と論文式試験でそれほど難易度が変わらないことが多いです。
ただ、理論問題や他の科目の対策に時間を割いていると、計算力は日に日に衰えていくため、短答式試験時の計算力を維持する心持ちで定期的に復習することをおすすめします。
監査論
監査論は、他の科目と比べてもボリュームが小さく対策が取りやすい科目です。
短答式試験で監査論の基本を理解した人であれば、答練や模試などで論文問題を繰り返し解き、論述練習や理解の定着を進めれば問題ないでしょう。
企業法
公認会計士試験の企業法は、論述練習の対策が特に需要となる科目です。
企業法の模範解答には定まった骨格があり、対策するうえではこの骨格を押さえることが非常に重要となります。
答練や模試の模範解答の文章構成をしっかりと理解して、どんな問題でもその構成(骨格)に当てはめて解答できるよう、アウトプット中心に学習を進めましょう。
企業法で出題される論点はそれほど幅広くはありませんが、解答が長文のため、そのすべてを暗記することは現実的ではありません。
典型論点については、参照基準や論点の趣旨などを押さえておき、本番試験時に解答の骨格に合わせアウトプットできるよう勉強しておきましょう。
租税法
公認会計士試験の租税法は暗記すべき内容も多く、計算問題では繰り返しの反復練習が求められる科目です。
短答式試験の試験範囲にはなかった新しい科目ということもあり、受験生間でも得意・不得意が分かれやすく差のつきやすい科目でもあります。
そのため、苦手科目として差を付けられてしまわないようしっかりと勉強することをおすすめします。
対策にあたっては、理論問題はあまり深追いせず時間をかけないようにしましょう。
理論問題は範囲が非常に広くどこまでも勉強できしまいますが、配点や出題内容を加味すると、理論で大きな差がつくことは考えにくいためです。
一方で、租税法の計算問題は基礎的な問題が中心ですので、基礎問題をクリアしておけば、高得点も狙うことができます。
理論問題の勉強に時間をかけすぎない分、計算問題にみっちりと時間を費やし勉強しておきましょう。
選択科目(経営学)
公認会計士試験の経営学は出題論点もある程度絞られており、出題難易度もそれほど高くありません。
一方で、高得点を狙おうとすると、勉強すべき範囲にキリがないため、必要以上に勉強時間を取られすぎてしまうリスクがあります。
そのため、経営学の勉強に際しては、正答率の高い基礎問題は確実にクリアすることを目標とし、あまり勉強時間をかけすぎずに、合格ラインの得点率付近を狙いにいくことをおすすめします。
勉強方法としては、テキストをざっと一通り目を通したうえで、答練や模試を中心に勉強することが最も効率が良いでしょう。
独学より公認会計士講座の受講がおすすめ

公認会計士試験を独学で突破することは簡単ではありません。
実際にほとんどの受験生が専門学校・予備校に通っており、独学の受験生の割合は非常に小さいのが実態です。
私自身、費用の面で融通が利くのであれば独学ではなく公認会計士講座を受講して勉強することをおすすめしています。
公認会計士講座の受講をおすすめする理由は次のとおりです。
専門学校・予備校のテキストや参考書は優秀
専門学校のテキストや参考書は、試験の出題傾向や対策をもとに毎年アップデートされており、試験用の勉強教材として非常に優秀です。
独学の場合、市販の教材・参考書では、公認会計試験用として出版されていないものも多く、どの点を重視して勉強すればよいのか分からない本も少なくありません。
また、ほとんどの受験生が専門学校のテキストのみを利用していることから、専門学校から配布されたテキストだけに集中して勉強していれば、テキストの面で、他の受験生に後れを取ることもないという点が、専門学校が支持される理由の一つです。
勉強の計画を任せることができる
独学の場合、試験に出題されにくい範囲の勉強をしてしまったり、難しい内容の勉強から始めてしまって挫折してしまうこともあり、学習スケジュールを立てるだけでも簡単ではありません。
一方で、専門学校の公認会計士講座では初学者向けの基礎的な内容から、本試験レベルの内容まで一定のカリキュラムに学習を進めていくことになります。
そのため、受講生は決められた学習カリキュラムに沿って講座を受講するだけで、初学者の人であっても、基礎的な内容から計画的に勉強を始めることが可能です。
自分で勉強の計画を立てる時間も節約でき、正しい方向で効率的な勉強を進められることから専門学校は根強く支持されています。
法改正に対応できる
公認会計士試験の試験範囲では毎年のように法規制の改正があり、受験生はその対応が必要になります。
専門学校では、改正論点の対策テキストや講座の対応もしてくれるため、自分で直近の改正内容などを調査する必要がありません。
独学の場合には、通常の試験範囲の勉強に加え、法改正の内容を自ら調査して勉強する必要があり、そこに不安を感じる受験生も少なくありません。
この点も専門学校が支持される理由の一つです。
まとめ
本記事では公認会計士試験の科目別の勉強方法を解説させて頂きました。
公認会計士試験は、範囲も膨大で難易度も高い難関試験です。
ただ、漫然と勉強しているだけでは他の受験生の先を走ることは難しいです。公認会計士試験の科目別勉強法をしっかりと理解したうえで、学習を進め合格目指して頑張りましょう。