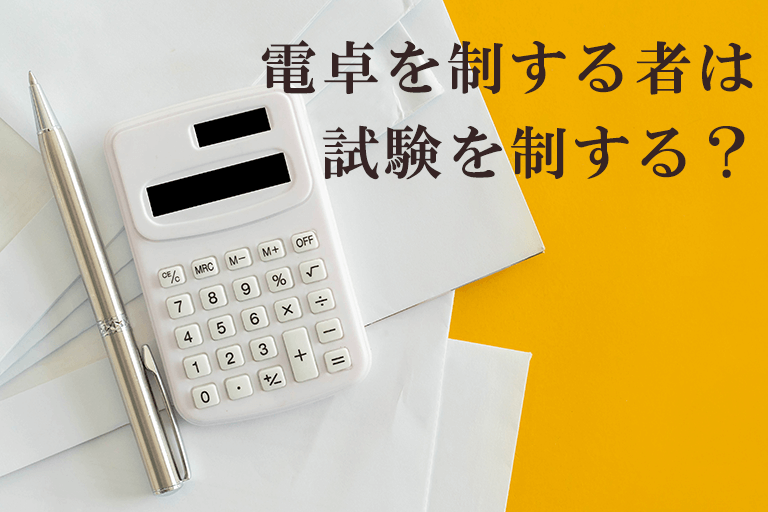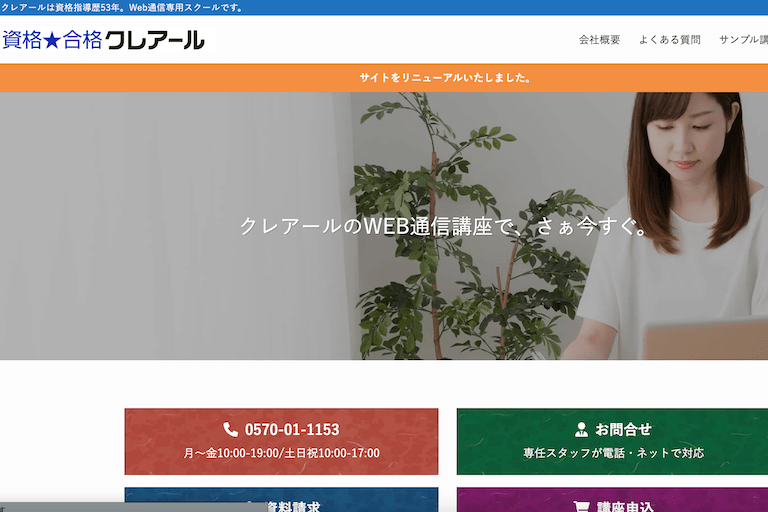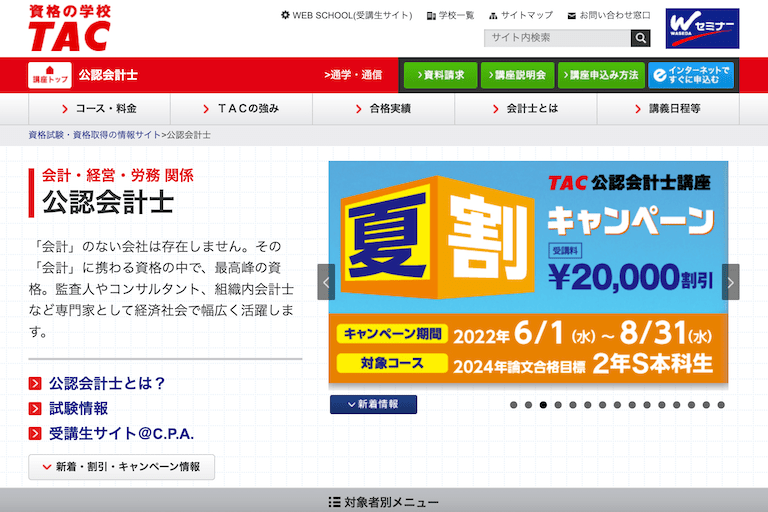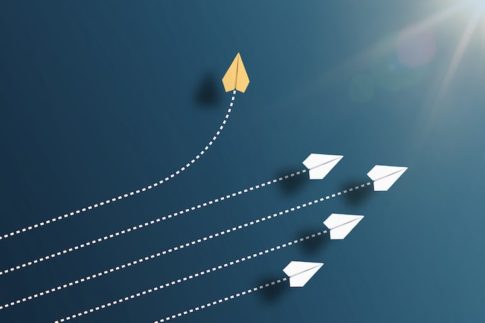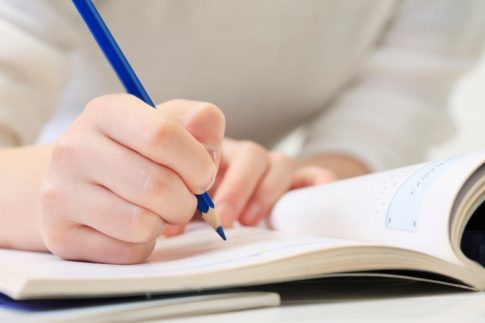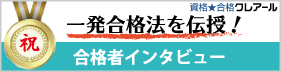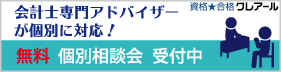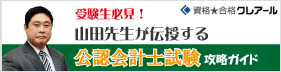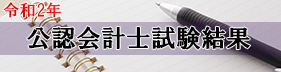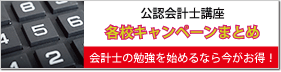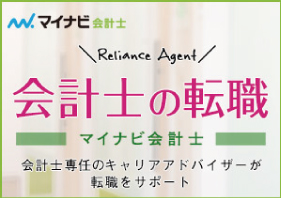公認会計士試験や税理士試験、簿記検定などの会計系の試験には電卓が必需品となります。
電卓には様々な機能が備えられていますが、全ての機能を使いこなせているという人も少ないのではないでしょうか。
公認会計士試験や簿記検定などの会計系試験は時間との勝負であり、電卓の機能を正しく使いこなせるか否かで試験の結果は大きく左右されます。
そこで、本記事では公認会計士試験などの会計系の試験で知っておくと便利な電卓機能一覧を詳しく解説します。
また、公認会計士試験におすすめの電卓や電卓上達のポイントについても紹介していきたいと思います。
便利な電卓機能一覧
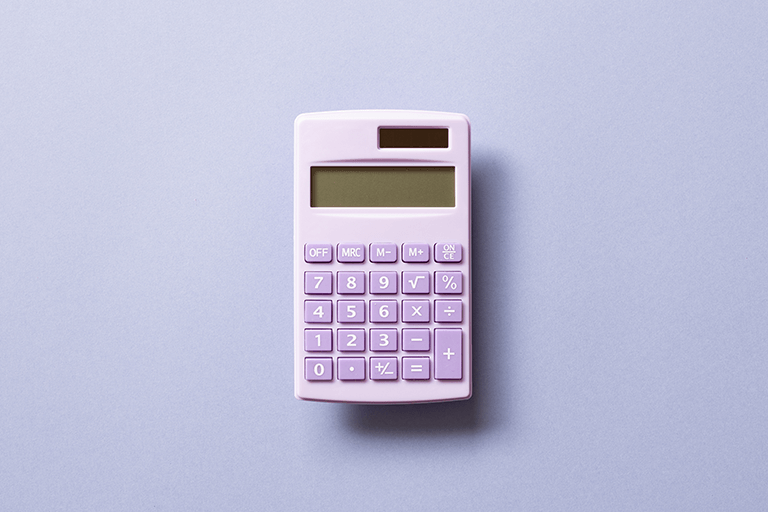
公認会計士試験や簿記検定において特に重要な電卓の機能とその概要は以下の通りです。
12桁表示
電卓画面の数値が12桁まで表示される機能です。
多くの公認会計士試験受験生は12桁表示のものを使用しています。
公認会計士試験では億円単位の問題も多く出題されるため、12桁以下の電卓では対応できない問題もあります。
必ず12桁表示の電卓を選ぶようにしましょう。
早押し機能
キーロールオーバー機能とも言われます。
キーの同時押しができる機能になります。
例えば、1⇒2とキーを押す場合に、2を押す前に1のキーから指を離さず1と2を同時押しする状態になっても、適切に1⇒2と認識できる機能を言います。
電卓の入力スピードが速くなってくると、ほとんど同時押しのような状況になりますが、その場合でも正確に認識できる機能ですので、公認会計士試験受験生は早押し機能が付いた電卓を選びましょう。
メモリー機能
電卓での計算結果を一時的に保存できる機能です。
このメモリー機能はM+、M-、MR、MCのキーで使用することができます。
| ボタン | 機能 |
|---|---|
| M+ | 画面上の数値または計算結果をメモリーに加算します。 |
| M- | 画面上の数値または計算結果をメモリーから減算します。 |
| MR | 記憶したこれまでの計算結果を画面上に表示します。 |
| MC | 記憶したこれまでの計算結果をクリアします。 |
例えば、100×2+50×3を計算をする場合に、100 ×2⇒「M+」⇒ 50 ×3⇒「M+」⇒「MR」の順でキーを押すことで計算結果である350を表示することができます。
この機能は公認会計士試験において使用する場面は非常に多いので、絶対に覚えておきましょう。
GT機能
グランドトータル(GT)機能といいます。先にご紹介したメモリー機能と同じく、計算結果を一時的に保存することができる機能です。
具体的には、[=]を押した後の数値(小計)を電卓内に加算して記憶し続けてい機能で、最終的に小計の合計を求めたい場合に使用します。
例えば、100×2+50×3を計算をする場合に、100×2⇒「=」⇒50×3⇒「=」⇒「GT」の順でキーを押すことで計算結果である350を表示することができます。
GT機能とメモリー機能の「M+」と何が違うのかと疑問を持たれた方も多いと思います。
実際のところ「それぞれの計算結果を加算して合計をもとめる」という意味で違いはありません。
メモリー機能では「M-」で減算することができるため、メモリー機能の方が汎用性が高いといえるでしょう。
そのため、GT機能は便利で使える機能ではありますが、メモリー機能で代替可能ですのでなくても問題はない機能といえるでしょう。
日数計算機能
その名の通り日数を計算できる機能で、例えば「10月21日」から「1月15日」までが何日あるかを計算することができます。
日数計算機能は、公認会計士試験ではあまり使用機会は多くなく、電卓を使わなくとも計算できることから、電卓での日数計算を使いこなしていない受験生も少なくありません。
電卓での計算方法は、例えば「10月21日」から「1月15日」までの日数を計算する場合には、以下の順でキーを押せば計算結果である86日を表示することができます。
「日数(月・日)」⇒10⇒「日数(月・日)」⇒26⇒「~」⇒1⇒「日数(月・日)」⇒15⇒「=」
√(ルート)計算機能
その名の通りルート計算をする機能です。
平方根を求めたい数値を入力⇒√(ルート)キーを押すことで入力した数値の平方根が画面に表示されます。
公認会計士試験では、ほとんど使う機会はないですが、知っていると便利なときもありますので、頭の片隅で覚えておくことをおすすめします。
税率計算機能
消費税の税抜き金額から税込み金額を計算したり、反対に税込み金額から税抜き金額を計算できる機能です。
公認会計士試験ではほとんど使用機会はありませんので、税率計算機能がついていない電卓を選んでも問題はないでしょう。
シャープとカシオで機能・使い方の違いは?
基本的にはシャープやカシオなど、どのメーカーも電卓としての機能やその使い方に違いはありません。
最も大きな違いはキーの配置が違うことでしょう。
キー配置は好みが分かれる部分ですので、試し打ちをしてみて自分に合ったキー配置の電卓を選ぶのが良いでしょう。
その他には、電卓のデザインや打鍵感、ディスプレイの大きさなどを比べてみて、自分の好みに合った電卓を探すことをおすすめします。
公認会計士試験で禁止されている機能
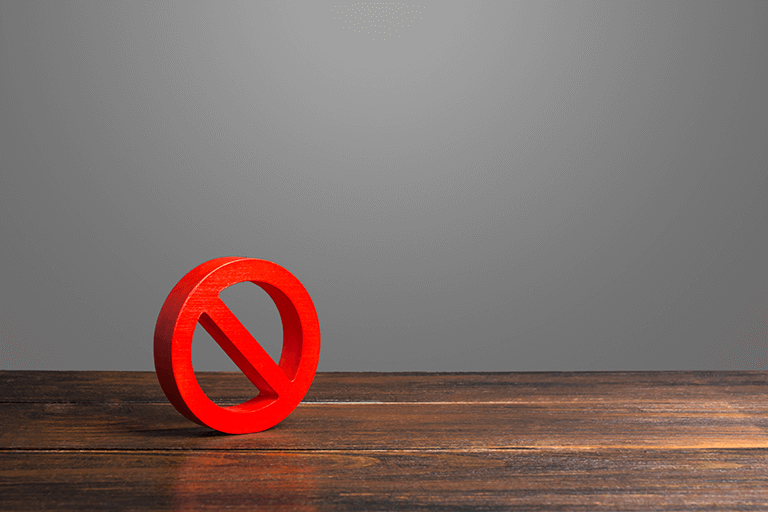
公認会計士試験や税理士試験、簿記検定などの会計系試験では基本的には以下の機能のついた電卓の持ち込み・使用は規定で禁止されています。
会計系試験を受験する方は次の機能がついていない電卓を選びましょう。
- 関数機能
- 辞書機能
公認会計士・簿記試験におすすめの電卓メーカー
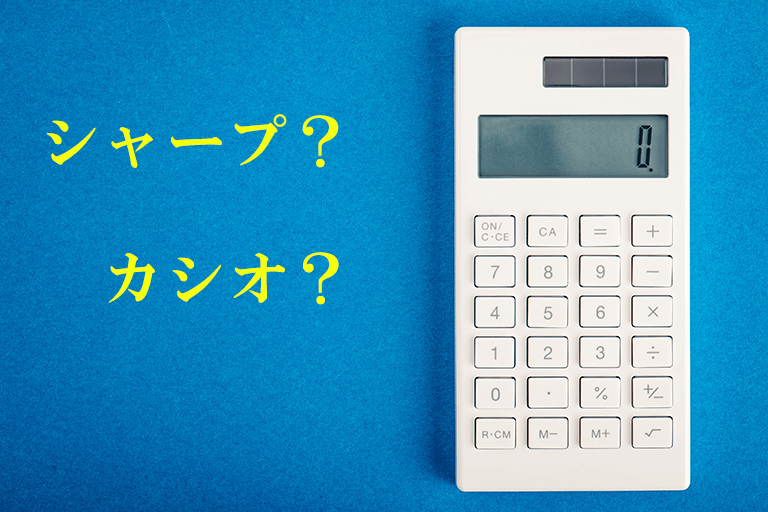
公認会計士試験や税理士試験、簿記試験などの会計系試験で、特に人気の電卓メーカーはシャープとカシオの2つでしょう。
電卓の機能や使い方はメーカーごとの違いはほとんどありませんが、どのような違いがあるのでしょうか。
電卓を選ぶ際に注目したいポイントについてメーカーごとの商品特徴とともに解説します。
シャープ(Sharp)
シャープはカシオと並ぶ電卓の人気メーカーです。
電卓としての機能性や価格帯でもシャープとカシオとの間に違いはほとんどありませんが、最も違いがあるポイントは電卓のキー配置です。
シャープの電卓のキー配置は右側に四則演算キー、左側に数値キー、上側にその他機能に関連したキーが並んでいます。
シャープの場合、キーが役割や機能ごとにグルーピングされて配置されているため。
電卓が不慣れな方にも馴染みやすいキー配置となっているかと思います。
カシオ
カシオもシャープに負けず劣らずの人気メーカーです。
カシオの電卓のキー配置は、数値キーが電卓の真ん中にあり、その周囲に四則演算キーやその他機能キーが配置されているという特徴があります。
カシオの電卓では指のホームポジションとなる数値キーが真ん中にあるため、キーの場所を感覚で覚えることができる方にとっては、少ない動きで電卓の端のキーも打つことができるので、早打ちがしやすいとも言われています。
予備の電卓のすすめ
試験中の電卓のトラブル(電池切れや故障)などに備えて、予備の電卓を購入することをおすすめします。
電卓の故障などで、代替機を使用することになった場合、メーカーが違えばキー配置も異なってしまい、いつも通りの感覚で電卓を扱うことも難しくなるでしょう。
1分1秒を争う公認会計士試験において、少しでも懸念事項を減らしておきたい方は、同じメーカーの同じタイプの電卓をそろえておくと安心して試験に臨むことができるでしょう。
試験合格のために上達のポイント

公認会計士試験や簿記検定などは時間との勝負です。
膨大な計算問題に時間内に回答するためには、電卓の上達は必須といえます。
こちらでは、公認会計士試験や簿記検定で必須となる電卓スキルの上達のポイントについて解説します。
左打ちは必須?
右利きの方は左手で、左利きの方は右手で、利き手とは逆の手で電卓を打つことを練習することをおすすめします。
体感ですが、実際に受験生の6-7割は右手にペンを持ち、左手で電卓を打っている印象です。
なぜ左手打ちが人気なのでしょうか。
一番の理由は、左手打ちの方が早く問題を解けるからです。
右利きの方の場合、右手でペンを持ち、解答用紙への記入や問題用紙のページをめくったりなどは右手で行うことが一般的です。
そうすると、電卓を右手で打つ場合、電卓から手を放して問題用紙や解答用紙との行ったり来たりが必要になってきます。
一方で、左手で電卓を打つ場合には、左手はずっと電卓の上に置いておくことができ、右手で解答用紙への記入などを行うことができます。
また、試験に合格し公認会計士として働くことになったときにも、資料をめくったりメモを取りながら電卓を打つ機会は少なからずあります。
左手打ちも最初は難しくとも、慣れればスムーズにできることが多いので、左手打ちで訓練することをおすすめします。
ブラインドタッチのコツは?
パソコンのブラインドタッチと同じで、まずは指のホームポジションの感覚を身につけましょう。
数字の「5」のボタンにポッチがついていると思いますが、それが中指を置く場所です。
そして「4」には薬指、「6」には人差し指を置くことになります(左打ちの場合)。計算のたびに、まずはこのホームポジションに指を置くことを徹底しましょう。
そして、ボタンごとにどの指が担当するかを決めることが重要です。
ホームポジションを始点として、「5」の列は中指で、「4」の列は薬指で、「6」の列は人差し指でという形で列ごとにどの指が担当するかを決めて、その役割を守るよう繰り返し練習を重ねましょう。
そうすると自然とブラインドタッチができるようになっていきます。
早打ちのコツは?
公認会計士試験や簿記検定は時間との勝負ですので、少しでも早く電卓を打てるようになりたいという受験生も多いと思います。
左打ちやブラインドタッチも重要な要素ですが、そういった受験生にまずおすすめしたいのが、正確に電卓を打つことを徹底的に意識することです。
限られた試験時間のなかで、電卓を早く打ちたいあまり焦ってしまいミスタイプを連発していることはないでしょうか。
一度計算をミスしてしまうとまた一から計算をやり直す羽目になるため、結局は慎重に電卓を打ったほうが早いということが多くあります。
また、電卓の計算ミスをしたまま回答してしまった場合には、時間をかけて解いたのに、点数はもらえないという最悪の事態も考えられます。
そのため、電卓を焦って早く打つのではなく、なによりも正確にキーを打つことを意識することが、電卓早打ちの近道となるのです。
まとめ
本記事では、公認会計士試験や税理士試験、簿記検定などの会計系の試験において、知っておくと便利な電卓の機能の一覧をご紹介しました。
電卓には様々な機能が備えられており、それを使いこなせるか否かで試験の結果は大きく左右されます。
また、公認会計士試験や簿記検定などにおすすめの電卓メーカ―(シャープ、カシオ)や電卓上達のポイントについても紹介をさせて頂きました。
本記事で紹介した電卓の便利機能や上達のポイントをしっかり押さえて頂き、公認会計士試験合格を目指す受験生の一助となれば幸いです。